プレゼン資料、YouTubeのスライド、企画書や報告書。
情報を伝える手段として「視覚化」が求められる場面は年々増えています。けれど、それを一からデザインするのは、手間も時間もかかる――。
そんな常識を、大きく覆す技術が登場しました。
GPT-4oの画像生成機能。
この最新AIは、ただの「お絵描きツール」ではありません。
指示するのは、たった二つ。「何を伝えたいか(箇条書き)」と「どんな雰囲気で表現したいか」──それだけで、高品質なスライドがほぼ一瞬で生成されます。
本記事では、この革命的な機能を活用した「スライド自動生成」の実践例と、その背後にある技術、さらにSNSでのリアルな反応や応用術まで、幅広くご紹介します。
もはや「AIに資料を任せる時代」は、未来ではなく現在。
あなたの時間と創造力を解放するための第一歩、始めてみませんか?
GPT-4oでスライド作成が劇的に変わる!画像生成AIの使い方と活用術
プレゼンや動画用にスライドを作る時間、削減したいと感じたことはありませんか?そんなときに注目したいのが、OpenAIが提供するGPT-4oの画像生成機能です。今回は、この機能を使って、箇条書きと雰囲気指定だけでハイクオリティなスライドを量産する方法を解説します。さらに、SNSでの反応や応用テクニックまで掘り下げていきます。
次章では、GPT-4oの画像生成機能の概要と基本的な使い方を見ていきましょう。
GPT-4oの画像生成機能とは?
無料プランでも使える?使い方の基本
GPT-4oは、OpenAIの最新モデルで、テキストに加えて画像や音声の生成にも対応しています。画像生成機能は基本的にすべてのプランで順次開放されていますが、利用可能になるまで若干のラグがあるようです。待てない人は、有料プラン(月額20ドル)の利用を検討しても良いでしょう。
使い方は非常にシンプルです。「画像を作成する」ボタンをクリックし、プロンプトを入力するだけで画像が生成されます。テキスト内に「スラッシュイメージ(/image)」と入れることで画像生成を明示することも可能です。
スラッシュイメージ(/image)コマンドや対話的な修正も便利
GPT-4oの画像生成で特筆すべきは、生成後の対話的な修正が可能な点です。たとえば「もう少し明るくして」「このキャラを削除して」などとリクエストすれば、即座に反映されます。特定箇所だけを選択して変更を指示することもできるため、微調整にも対応できるのが魅力です。
次は、画像生成に特化した別ツール「空(くう)」の機能について紹介します。
ChatGPTだけじゃない!「空(くう)」の実力と使い分け
アスペクト比固定が神。3:2や1:1対応もOK
「空」は、ChatGPTの左上メニューからアクセスできる画像生成ツールです。最大の特長は、アスペクト比の固定ができる点。スライド作成では、横長(16:9)や縦長(9:16)といった画面比率が重要ですが、空では1:1、3:2、2:3などから選ぶことができ、指定通りに生成されます。
一方、ChatGPT本体で「16:9にして」と頼んでも、なぜか正方形画像が出てくることもあり、やや不安定です。そのため、初期生成は空を使い、細かな修正はChatGPTで行うという使い分けが最適です。
修正はChatGPTと連携すれば完璧
空で生成した画像をダウンロードした後、ChatGPTに読み込ませて「この部分を変更して」と伝えれば、高精度な画像修正が可能です。たとえば「吹き出しのセリフを変えて」「背景を暗くして」などの依頼が通ります。これにより、用途に応じた微調整もスムーズに行えます。
それでは、実際にどのような手順でスライドを作るのか、次の章で具体的に見ていきましょう。
実践!メタプロンプトでスライド量産の流れ
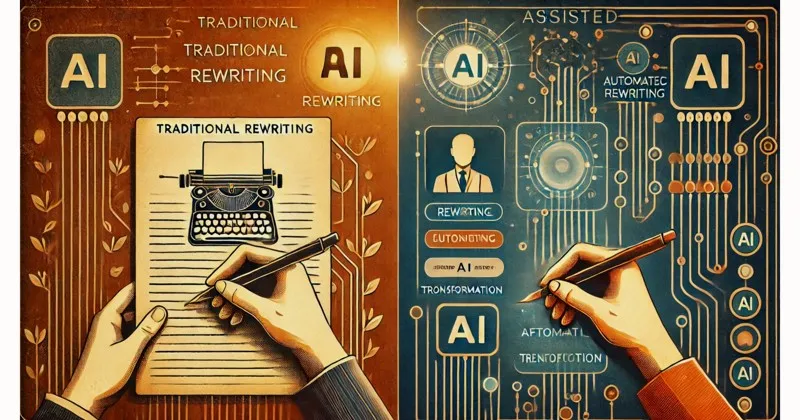
箇条書き+雰囲気指定だけで自動作成
GPT-4oでスライドを作るためには、「スライド作成プロンプト」を作るための「メタプロンプト」を使います。たとえば「スライドで伝えたい内容(箇条書き)」と「テイスト(雰囲気)」の2点を指定するだけでOKです。
例:
- 箇条書き:AIでスライド作成が可能/プロンプトだけで生成/手間が激減
- 雰囲気:暗めのデジタル感がある背景/ポップな色合い/親しみやすい印象
この情報をプロンプトとして入力すると、スライドに適した画像と構成が自動的に生成されます。
引用:https://note.com/ai_saborou/n/nabeadc550bec
あなたは教育資料のビジュアル設計者です。台本のセリフを分析し、一枚のスライドとして表示すべき視覚資料を設計する役割を担っています。以下の台本のセリフを分析してください:
スライドのスタイルは以下の通りです:
分析プロセス
- まず、タグの中で台本を分析し、以下を特定してください:
- 重要な概念や用語
- 説明が必要な複雑なプロセスや関係性
- 数値データや統計情報
- 比較や対比が必要な要素
- 特定した各ポイントについて、一枚のスライドで最も効果的に視覚化できる方法を検討してください:
- テキストオーバーレイ(重要な用語や定義)
- 図表やチャート(データや統計)
- フローチャートやプロセス図(手順や関係性)
- イラストや写真(具体的な概念や例)
- 比較表(類似点や相違点)
設計要件
- 視覚資料はシンプルで明瞭であること
- スライドのスタイルに適合した色彩やフォントを使用すること
- 一画面に表示する情報量は適切であること(情報過多にならないよう注意)
- 台本の内容を効果的に一枚のスライドに集約すること
- 視聴者の理解を助けるものであること
出力形式
あなたの回答は以下の構造で提出してください:
- タイトル: [スライドのタイトル]
- タイプ: [テキストオーバーレイ/図表/フローチャート/イラスト/比較表など]
- 内容: [表示すべき具体的な内容、テキスト、要素などの詳細]
- デザインポイント: [配色、レイアウト、フォントなどの特記事項]
例
台本:「太陽光発電の仕組みは、太陽の光エネルギーを半導体で電気エネルギーに変換するというものです。この過程では、光子が半導体に衝突して電子を放出し、電流が生まれます。」
- タイトル: 太陽光発電の仕組み
- タイプ: プロセス図 + テキストオーバーレイ
- 内容:
- 中央に太陽→太陽光パネル→変換器→電気の流れを示す図
- 各要素にラベル付け
- 右下に半導体内部の拡大図(光子が半導体に当たり電子が放出される様子)
- 主要ポイントを箇条書きで表示:
- 太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換
- 光子が半導体に衝突
- 電子放出により電流が発生
- デザインポイント:
- 背景は濃紺のグラデーション
- 青と黄色のコントラストで視認性を高める
- 光の経路は黄色の点線で表現
- モダンでクリーンなサンセリフフォント
- 重要用語は太字でハイライト
「暗めデジタル×ポップ」などテイスト調整も自由自在
さらに、色味やタイポグラフィーなどを細かく定義することで、デザインの統一性を持たせることも可能です。逆に、あえてざっくりした雰囲気指定にすることで、スライド間の“ゆらぎ”を楽しむ方法もあります。動画の背景など、画面の変化を持たせたい場面では、このゆらぎが効果を発揮します。
スライドの品質は90点超え?実力75点の筆者も感動
筆者自身もこの機能を使って動画用スライドを制作してみましたが、仕上がりは「自分で作るより良いのでは?」と感じるレベルでした。プロのデザイナーが100点とするなら、GPT-4oは90点、自作は75点といったところでしょう。
では、スライド画像を動画にも活用したい場合はどうするのでしょうか?次はレイヤー出力の応用について紹介します。
レイヤー出力でアニメ素材にも!

吹き出し・ロボット・背景を別々に出力可能
スライド画像をより活用するなら、レイヤーごとに素材を分解する手法がおすすめです。GPT-4oに対して「吹き出しだけをPNGで出して」「背景だけ出力して」などと順番に依頼すると、それぞれの要素を個別に取得できます。
1回で複数のレイヤーを同時出力することはできませんが、数回に分ければ問題ありません。多少手間はかかるものの、仕上がりの自由度が一気に上がります。
Canvaなどで動かせば、スライドから動画まで対応
こうして取得した素材を、CanvaやPowerPoint、AfterEffectsなどに取り込めば、アニメーション付きの動画として活用することも可能です。たとえば、ロボットが喋る/吹き出しがフェードインする、といった動きも簡単に実装できます。
では、こうした技術に対してユーザーはどんな反応を示しているのでしょうか?SNSやコメント欄の声を次に見ていきましょう。
SNSやコメント欄の反応は?みんなの本音と使いどころ
実際のコメントで多かった声
GPT-4oによるスライド生成に対して、SNSやコメント欄では次のような声が寄せられています:
- 「資料作成、マジで一瞬で終わった」
- 「クオリティ高すぎて自分で作る気なくなる」
- 「無料プランだと画像生成できないって本当?」
特に業務用途で使っているユーザーからは、「もはや人力より早い」「スライドづくりの概念が変わる」といった驚きの声が多数上がっています。
読者・視聴者に伝えたいこと
AIによる自動生成は、単なる「手間の削減」ではありません。それは、アウトプットの質とスピードの両立を可能にする新たな手段です。
今後、「手間をかけない=手抜き」と考えるのは時代遅れになるかもしれません。AIはもはや“補助輪”ではなく、必要に応じて“代打”を任せられる存在です。
これからの時代、あなたはどのタスクをAIに任せますか?

コメント