「Obsidianに溜めたメモ、AIでどう活用すればいい?」「設定が複雑で挫折しそう…」。そんな悩みを解決するため、この記事では「cursor obsidian 使い方」を徹底解説します。
単なる機能紹介ではなく、情報収集からアウトプットまで、あなたの知的生産を革新する具体的なワークフローを提案。最新AI(LLM)の力を借り、非エンジニアでも実践できる手順で、あなたのメモを最強の知識資産に変えましょう。
✅この記事を読むとわかること
- ObsidianとCursorを組み合わせる本質的な理由
- AIを活用した情報収集からアウトプットまでの全手順
- 非エンジニアでも挫折しないPCとスマホの連携方法
- 自分の仕事に合わせた具体的なカスタマイズの方向性

⚠️本記事で使用した画像は説明のためのイメージ画像です。実際のデザインとは異なる場合があります。
- Obsidian(知識の保管庫)とCursor(AIの作業場)の連携で、知的生産が劇的に変わります。
- 情報収集から執筆、ファイル整理まで、全ワークフローをAIで自動化・効率化できます。
- 最もつまずきやすいPCとスマホの同期も、AIと対話しながら安全に設定できます。
- 面倒な「整理」から解放され、人間は「思考」という最も創造的な活動に集中できるようになります。
なぜ最強?cursorとobsidian の使い方を思想から理解
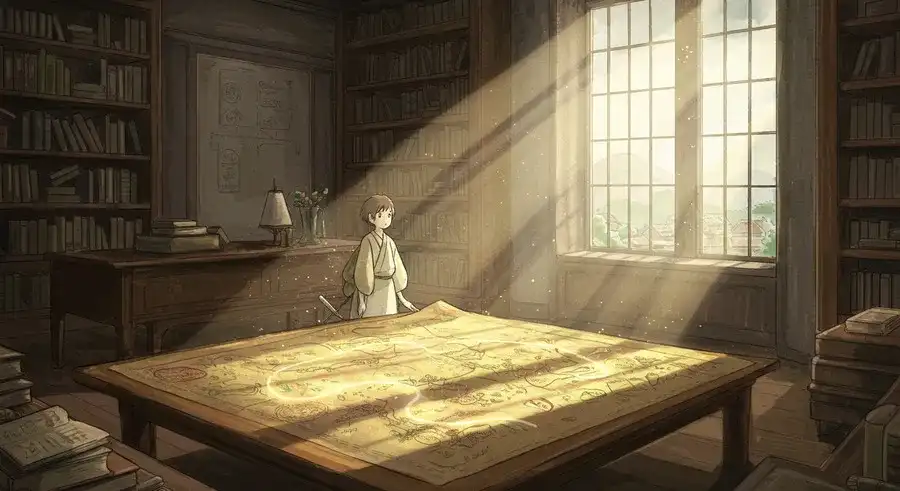
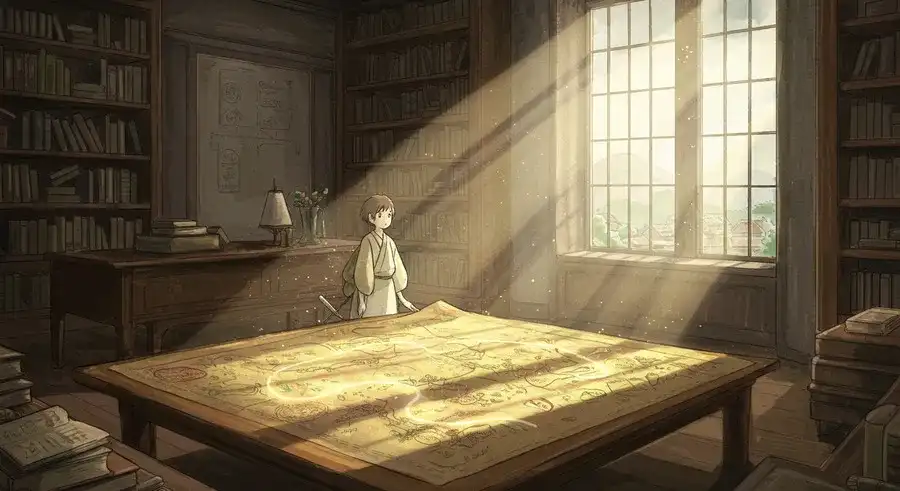
ここでは、単なる機能紹介を超え、ObsidianとCursorがなぜ最強の組み合わせなのかを「思想」のレベルから解説します。この連携があなたの知的生産の常識をどう変えるのか、その本質を理解しましょう。
保管庫(Obsidian)× 実行環境(Cursor)


たくさんのメモツールに情報が散らばり、「あの情報はどこに書いたっけ?」と探すことに疲れていませんか。せっかくメモをしても、ただ保管するだけでは知識の価値は半減してしまいます。大切なのは、必要な時にすぐに取り出し、活用できる仕組みを作ることです。
この課題を解決する鍵は、「保管する場所」と「活用する場所」を明確に分けるという考え方にあります。
知識を永続させる「保管庫」としてのObsidian
まず、Obsidianをあなたの知識を安全に蓄積するための「保管庫」と位置づけます。
Obsidianの大きな特徴は、データがあなたのパソコン内に直接、Markdownというシンプルなテキスト形式で保存されることです。これにより、サービスが終了する心配や、意図せず情報が漏洩するリスクを最小限に抑えられます。
また、ノート同士を[[ノート名]]という記法で簡単につなげられるため、知識が自然とネットワークのように結びついていきます。まさに、あなたの思考や学びを永続的に育てていく「第二の脳」を構築するのに最適な場所なのです。
思考を形にする「実行環境」としてのCursor
次に、Cursorをその保管庫から知識を取り出し、AIと共に活用するための「実行環境」と考えます。
Cursorは、Obsidianの保管庫(フォルダ)をそのまま開くことができます。これは例えるなら、巨大な図書館(Obsidian)の中から必要な本を数冊選び出し、優秀なAIアシスタントがいる自分の作業机(Cursor)に持ち込んで、じっくりと研究するようなものです。
保管されたメモをAIに要約させたり、新しい記事の構成案を作らせたり、あるいは複雑な文章を分かりやすく書き直させたりと、思考を具体的な形にするためのあらゆる作業をAIがサポートしてくれます。
なぜこの役割分担が理想的なのか
このように、「保管」に特化したObsidianと、「実行」に特化したCursorを組み合わせることで、知識が死蔵されることなく、常に行動や創造に結びつくようになります。
情報が安全に蓄積され、かつAIによっていつでも活用できる状態にある。この理想的な役割分担こそが、ObsidianとCursorの連携がもたらす最大の価値なのです。
「メモ整理」から「AIとの思考」へのパラダイムシフト


「完璧なフォルダ構成を考えようとして挫折した」「タグ付けのルールが複雑になり、結局続かなかった」といった経験は、多くの方がお持ちではないでしょうか。私たちはこれまで、ノートを「整理」することに多くの時間を費やしてきました。しかし、その時間は本当に創造的な活動だったのでしょうか。
この連携がもたらすのは、単なる効率化ではありません。あなたの知的生産に対する考え方そのものを変える「パラダイムシフト」なのです。
面倒な「整理」はAIの仕事
これからの時代、ノートの整理は人間の仕事ではなくなります。例えば、あなたが一日かけて集めたWeb記事のクリップやメモの山があるとします。
これまでは、一つひとつに目を通して分類し、タグを付ける必要がありました。しかしCursorを使えば、「このフォルダ内のメモを内容に応じてタグ付けして」と指示するだけで、AIがごく短時間で作業を完了させます。
このように、時間を奪っていた面倒な整理作業から解放されること。それが、この連携がもたらす第一の変化です。
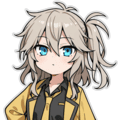
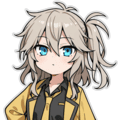
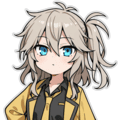
実際にはノート数やPCスペック、AIモデルの性能によって処理時間は変動します。
人間は最も重要な「思考」に集中する
では、整理作業から解放された人間は何をするべきなのでしょうか。答えは、AIとの「思考の壁打ち」です。
AIが整理してくれた情報を元に、あなたはより本質的な問いに時間を使えるようになります。
- 「先週のメモの中で、最も関連性の高い3つのアイデアを組み合わせて、新しい企画のコンセプトを提案して。」
- 「この技術レポートと、あのマーケティングレポートの共通点と相違点を分析し、ビジネスチャンスを教えて。」
AIが思考のパートナーとなることで、一人ではたどり着けなかったような深い洞察や、全く新しいアイデアが生まれる可能性が広がります。
思考のパートナーとしてのAI
ObsidianとCursorの連携は、あなたを「ノート整理係」から解放し、「AIを駆使する思想家」へと役割を変えてくれます。
ツールはもはや単なる記録媒体ではありません。あなたの思考を拡張し、共に創造するパートナーへと進化します。この新しい関係性こそが、これからの知的生産のスタンダードになるのです。
Notion等では難しい、ローカルLLM連携の可能性


Notionをはじめとするクラウド型のノートアプリは非常に便利ですが、「会社の機密情報」や「個人的な日記」といった繊細な情報を、外部のAIに読み込ませることに抵抗を感じる方も少なくないでしょう。便利なAI機能を使いたい、しかしセキュリティが心配だ、というジレンマは、多くの人が抱える課題です。
この根本的な不安を解消するのが、Obsidianの「ローカル保存」という仕組みです。
あなたのデータは、あなたの手の中に
Obsidianの最大の特徴は、作成した全てのノートが、特定の会社のサーバーではなく、あなた自身のパソコンの中に「.md」という拡張子のテキストファイルとして保存される点にあります。
これは、あなたがデータの完全な所有権を持つことを意味します。誰かが勝手にあなたのノートを閲覧したり、サービスの方針変更でデータが消えたりする心配がありません。この「手元にある」という絶対的な安心感が、Obsidianの思想の根幹をなしています。
未来の働き方:ローカルAIとの連携
このローカル保存という特徴は、AI技術の未来と結びつくことで、さらに大きな可能性を秘めます。それが「ローカルLLM(大規模言語モデル)」との連携です。
ローカルLLMとは、簡単に言えば「インターネットに接続せず、あなたのパソコンの中だけで動くAI」のことです。これとObsidianを組み合わせることで、クラウドサービスでは実現が難しい、次のようなワークフローが現実のものとなります。
- 機密情報の安全な分析: 会社の内部資料や顧客リストを、一切外部に送信することなくAIに分析させ、レポートを作成する。
- プライベートな自己分析: 誰にも見せたくない日記や創作メモをAIに読み込ませ、自分の思考パターンを分析してもらったり、アイデアの壁打ち相手になってもらったりする。
- 完全オフラインでの作業: インターネット環境がない飛行機の中やカフェでも、AIアシスタントと共に執筆や情報整理を進める。
なぜクラウドサービスでは難しいのか
クラウドベースのツールで同様のことを行うには、一度データを外部サーバーに送信する必要があり、プライバシーやセキュリティのリスクが伴います。
一方でObsidianは、あなたのPC内にあるデータを、同じくPC内で動くAIが直接参照するため、情報が外部に漏れる心配がありません。
プライバシーを守りながらAIの恩恵を最大限に享受したいと考えるなら、この「ローカル・テキストベース」というObsidianの構造は、他のどのツールにも代えがたい大きな利点となるのです。
あなたのワークフローはどう変わる?3つの革命
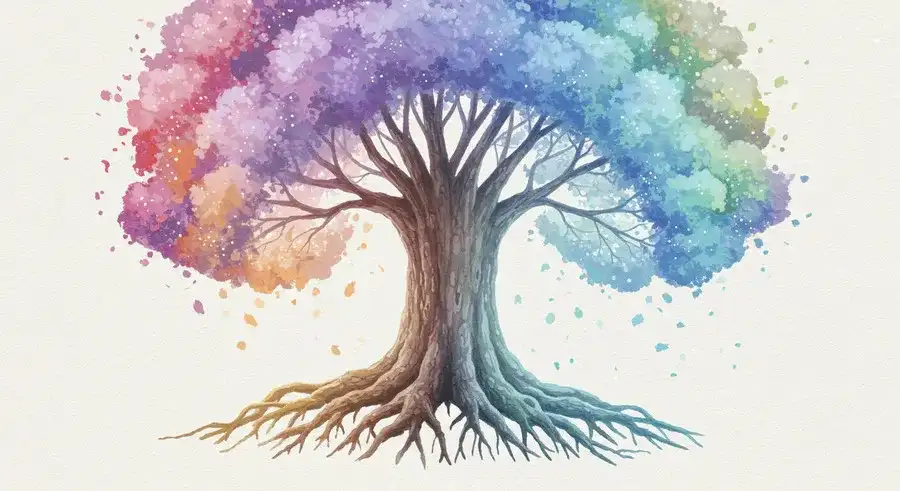
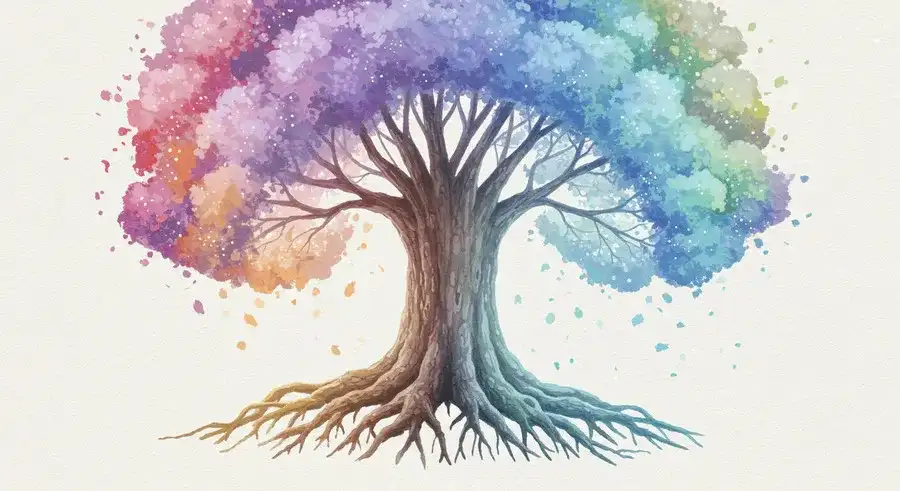
ここまでObsidianとCursorの思想的な背景をお伝えしてきましたが、「理論は分かったけれど、具体的に自分の仕事や生活がどう変わるのか、まだイメージが湧かない」と感じているかもしれません。
ご安心ください。ここからは、あなたの知的生産のプロセスに起きる「3つの革命」を予告します。これは、この後に続く実践的なワークフローを理解するための、いわば未来の地図です。
革命1:情報収集が「作業」から「習慣」へ
これまでは、Webで見つけた記事やKindleで引いたハイライトを「後で整理しよう」と思いつつ、結局そのまま放置してしまいがちでした。
しかし、これからは情報収集が半自動化されます。気になる情報はワンクリックでObsidianに集約され、AIがその内容を要約し、関連するタグまで付けてくれるようになります。「情報を集めて整理する」という意識的な作業から解放され、知識が無意識のうちにあなたの「第二の脳」に蓄積されていくのです。
革命2:アイデア出しが「苦悩」から「対話」へ
白紙のページを前に、何から書けばいいか分からず悩む時間はもうありません。
あなたのObsidianには、すでに多くの知識の種が蒔かれています。Cursorを使えば、それらの種をAIに示し、「これらの情報から、新しい企画のアイデアを5つ提案して」と問いかけることができます。アイデア出しは、一人で苦しむ作業から、優秀なパートナーとの「対話」へと変わります。
革命3:繰り返し作業が「手作業」から「自動実行」へ
週報の作成、ファイル名の整理、議事録のフォーマット統一。毎週、毎月のように繰り返される、創造的とは言えない作業に時間を奪われていませんか。
この連携を使えば、そうした定型作業を「ルール」としてAIに記憶させ、ワンクリックで実行させることが可能になります。あなたは面倒な手作業から解放され、その時間を本当に価値のある、創造的な仕事に集中させることができるのです。
これら3つの革命は、あなたを知的生産の「作業者」から、AIを駆使する「指揮者」へと変貌させます。さあ、その具体的な方法を、次のセクションから見ていきましょう。
実践!cursor obsidian の使い方を3つのフローで構築
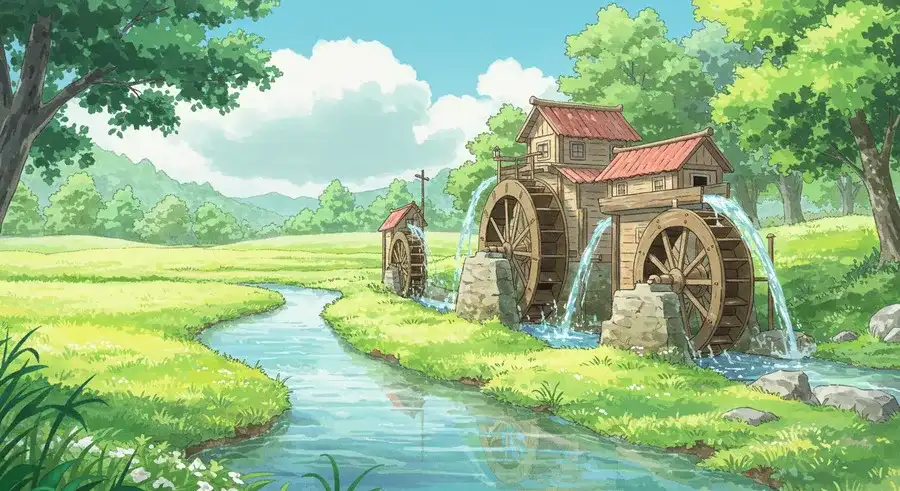
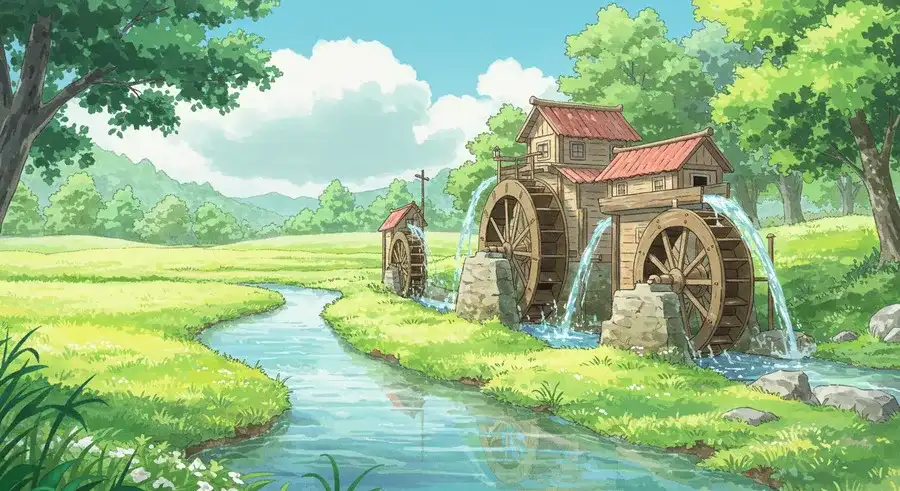
理論を理解したら、次はいよいよ実践です。ここでは、あなたの知的生産プロセスを「収集」「発想」「改善」の3つの具体的なワークフローに分解し、AIと共に実践する手順をステップバイステップで解説します。
【フロー1】収集と構造化:無意識に知識が貯まる仕組み


KindleやWebの情報をAIが自動で整理・要約
読書中に出会った心に響く一節や、仕事のヒントになるWeb記事。それらは本来、あなたの未来を豊かにする知識の宝のはずです。しかし、「後で読もう」と開かれた無数のブラウザタブや、ハイライトを引いたまま忘れ去られた電子書籍が、あなたの頭の片隅で重荷になっていませんか。
情報を「集める」だけで満足し、それを「活用」する手前の「整理」という高い壁に、多くの人が足止めされています。この面倒なプロセスを、AIに任せてしまいましょう。
まず、情報収集の入り口をObsidianに一本化します。
- Web記事の場合: Chromeの拡張機能「Obsidian Web Clipper」を導入します。気になる記事を見つけたら、アイコンをクリックするだけで、記事全文があなたのObsidianに保存されます。
- 読書の場合: Obsidianのコミュニティプラグイン「Kindle Highlights」を設定します。一度設定すれば、あなたがKindleで引いたハイライトやメモが、Obsidianを起動するたびに自動で同期されます。
この2つを設定するだけで、あなたの知的活動の記録が、何もしなくてもObsidianという保管庫に集まってくる仕組みが完成します。
情報が集まったら、次はCursorの出番です。集めた情報が入っているフォルダをCursorで開き、AIにこう指示してみましょう。
「このフォルダにある、ここ1週間のWebクリップと読書メモを分析して。それぞれのノートに内容を表すタグを3つずつ付け、全体を300字で要約して新しいノートにまとめて。」
AIは瞬時に全てのノートを読み込み、人間がやれば数時間はかかるであろう整理と要約の作業を、ものの数分で完了させます。
このフローを習慣にすれば、あなたは「情報を集める」という最も楽しい部分に集中するだけ。あとはAIが知識を整理し、いつでも取り出せるように構造化してくれます。もう、情報の死蔵に悩むことはありません。
挫折しない!GitHubを使ったスマホ同期環境の作り方
「PCでまとめた渾身のメモを、外出先のカフェでスマホから見返したい」「通勤電車で浮かんだアイデアを、すぐにObsidianに書き留めたい」。知的生産を加速させる上で、PCとスマホの連携は不可欠です。
しかし、無料でこれを実現できるGitHubを使った方法は、非エンジニアにとって「コマンド」「ターミナル」といった呪文のような言葉が並び、挫折ポイントの最たるものでした。
ですが、もしあなたの隣に、優秀なIT専門家が座って手取り足取り教えてくれるとしたらどうでしょう。その役割を、AIに担わせるのです。
この設定で大切なのは、分からないことを一人で抱え込まないことです。CursorやChatGPTのチャット画面を開き、正直にこう聞いてみましょう。
「Obsidianのデータを、GitHubを使ってPCとiPhoneで同期したいです。Gitやコマンドの知識は全くありません。私がやるべきことを、一つずつ、コマンドの意味も解説しながら、小学生に教えるように教えてください。」
この「魔法の質問」が、あなたを成功へと導きます。
AIは、あなただけの家庭教師として、次のように導いてくれるはずです。
- PC側の準備: AIの指示通りに、GitHubのサイトで「リポジトリ」という名のデータの保管場所を作ります。この時、「Private(非公開)」に設定するのを忘れないように、とAIは注意してくれるでしょう。
- Cursorでの魔法: 次に、難関のコマンド入力です。しかし、あなたは黒い画面を触る必要はありません。CursorでObsidianのフォルダを開き、AIに「このフォルダをGit管理下にしたいから、必要な初期設定をお願い」と伝えるだけです。AIが必要なコマンドを提案し、ユーザーが安全に実行できます。
- スマホ側の設定: 最後にスマホの設定です。AIが推奨するアプリをインストールし、「この画面では何を入力すればいい?」とスクリーンショットを見せながら聞けば、AIは的確な答えを返してくれます。
これまで専門知識と勇気が必要だった同期設定が、AIとの「対話」によって、安全かつ確実に実行できるようになりました。この最大の壁を乗り越えたとき、あなたのObsidianは、場所を選ばない真の「第二の脳」として機能し始めるのです。
【フロー2】発想と執筆:AIと思考の壁打ちをする技術


複数メモからAIが作る「構成案」がすごい
ブログ記事や企画書を作成する際、最も創造性が問われるのが「構成」を考えるプロセスです。関連する資料や過去のメモはたくさんあるのに、それらをどう結びつけ、読者を引き込む物語を紡げばいいのか。白紙のページを前に、思考が堂々巡りしてしまう経験は誰にでもあるでしょう。
この「無から有を生み出す」最も困難な作業を、AIとの共同作業に変えるのがCursorの@file機能です。
例えば、あなたが「AI時代の働き方」というテーマでブログ記事を書こうとしているとします。あなたのObsidianには、関連情報として以下のメモが保存されているとしましょう。
- A書籍の読書メモ.md
- B氏の講演会メモ.md
- 最新AIニュースのWebクリップ.md
これまでは、これらのファイルを一つひとつ開き、頭の中で情報を再構築する必要がありました。しかしCursorを使えば、その必要はありません。
CursorのAIチャット画面で、@に続けて上記3つのファイル名を指定し、こう指示します。
「これら3つのファイルを元に、『AI時代の必須スキル』というテーマでブログ記事の構成案を作成してください。読者の不安を煽るのではなく、希望が持てるような前向きな切り口で、タイトル案と導入、3つの章、まとめの骨子をお願いします。」
この指示を受け、AIは3つの文書を横断的に読み込み、それぞれの要点を統合します。そして、あなた一人の視点だけでは生まれなかったかもしれない、論理的で魅力的な構成案を提示してくれるのです。
例えば、A書籍の「スキルの陳腐化」という視点と、B氏の講演の「コミュニケーション能力の重要性」という視点、そして最新ニュースの「具体的なAIツール」を結びつけ、「AIを『部下』として使いこなすための3つのスキル」といった独自の切り口を提案してくれるかもしれません。
この機能は、構成案作成の時間を劇的に短縮するだけでなく、あなた自身の思考の盲点に光を当て、アイデアを新たな高みへと引き上げてくれます。ゼロから始める苦しみは、AIが提示してくれた「思考の地図」を元に、より良いルートを探すという創造的な探検に変わるのです。
コピペで使える!AIに書かせる魔法のプロンプト
「AIに文章を書いてもらったけど、なんだか機械的で心が動かない」。そう感じたことはありませんか。AIは非常に優秀ですが、こちらの意図を正確に伝えなければ、ありきたりの言葉しか返してくれません。
優れた文章をAIに書かせる秘訣は、AIに明確な「役割」と「文脈」を与える、具体的な指示、すなわち「魔法のプロンプト」にあります。ここでは、様々なシーンですぐに使えるプロンプト集をご紹介します。これらをコピー&ペーストし、あなたの言葉で少し調整するだけで、AIはあなた専属の優秀なライターに変わります。
あなたは読者の心に深く寄り添うことができる、経験豊富なWebライターです。以下の【要点】を元に、読者が「これは、まさに私のための記事だ」と感じ、続きを読むのが待ちきれなくなるような導入文を、異なる切り口で3パターン作成してください。
【要点】・ObsidianとCursorの連携に興味がある・設定が難しそうで一歩踏み出せない・知的生産を効率化したい
あなたは専門的な内容を、中学生にも理解できるように解説する名人です。「双方向リンク」というObsidianの専門用語について、身近な「友達の輪」に例えながら、その機能がなぜ画期的なのかを200字以内で説明してください。
あなたは好奇心を刺激するのが得意なSNSマーケターです。以下のブログ記事の魅力を伝え、読者が思わずクリックしたくなるような、X(旧Twitter)用の投稿文を5つ作成してください。インパクトのある言葉と、適切なハッシュタグを入れてください。
【記事の要点】・ObsidianとAIで知的生産が爆速化する・非エンジニアでもできるスマホ同期の方法を解説・具体的なワークフローを紹介
これらのプロンプトは、AIに単なる作業を依頼するのではなく、特定の「ペルソナ(役割)」になりきってもらうよう指示しているのがポイントです。AIとのコミュニケーションの質を高めることで、あなたの表現力は無限に広がります。
【フロー3】改善と自動化:未来の自分を助ける仕組み


AIにファイル整理やリネームを「相談」する
知的生産の活動を続けていくと、必ず直面するのが「ファイルの混沌」という問題です。初めはきれいに整理していたはずのノートも、いつしか命名規則がバラバラになり、「2024-05-20.md」というファイルと「240520.md」というファイルが混在するような事態に陥ります。
これを一つひとつ手作業で直すのは、想像するだけで気が遠くなる作業です。かといって、プログラミングで一括処理するのは、多くの方にとって現実的ではありません。この「面倒だが、放置もできない」というジレンマを、AIとの「相談」で解決しましょう。
難しそうなファイル操作も、専門家と一緒なら安心です。Cursorには「ターミナル」というコマンドを実行するための機能が内蔵されており、AIに相談することで、あなたに代わって複雑な操作を安全に行ってくれます。
例えば、バラバラになったデイリーノートのファイル名を統一したいと考えたとします。その際、CursorのAIチャットにこう話しかけてみてください。
「優秀なITコンサルタントとして相談に乗ってください。このフォルダにあるデイリーノートのファイル名を、すべて『YYYY-MM-DD』の形式に統一したいです。プログラミングは分かりませんが、安全に一括変更できる方法を教えてください。実行する前に、どんなファイルがどう変わるのか、必ず私に確認させてください。」
この指示を受けたAIは、あなたのために専用のコマンドを考え、その意味を丁寧に解説してくれます。
- AIが提案: 「承知いたしました。まず、ファイル名がどのように変更されるかを確認するための、安全なプレビューコマンドはこちらです。」と、コマンドを提示します。
- あなたが理解・承認: AIからの解説を読み、「この変更内容で問題ありません。実行してください」とあなたが承認します。
- AIが実行: あなたの承認を受けて初めて、AIがコマンドを実行し、ファイル名が一括で変更されます。
このように、AIと対話しながら進めることで、何が起きるか分からないまま実行してしまうというリスクを完全に排除できます。
ファイル整理はもはや、孤独な手作業でも、専門家だけのものでもありません。AIという頼れる相談相手と共に、あなたのナレッジベースを常に美しく、使いやすい状態に保ち続けることができるのです。



整理作業の多くをAIに任せることで、人間はより思考に集中しやすくなります
「ルール機能」で面倒な定型作業をワンクリック化
あなたの仕事の中には、創造的ではないけれど、毎週・毎月のように繰り返される「定型作業」が存在しないでしょうか。
例えば、「週末にその週のデイリーノートを振り返り、未完了のタスクを洗い出す」「議事録を会社の公式フォーマットに整形する」といった作業です。これらは重要ですが、繰り返すうちにあなたの貴重な時間とエネルギーを少しずつ奪っていきます。
もし、これらの作業を完璧にこなしてくれる「あなた専用のアシスタント」がいたらどうでしょう。Cursorの「ルール機能」は、まさにそのアシスタントをAIで作り出すための仕組みです。
「ルール機能」とは、一連の作業指示を「指示書ファイル」としてAIに記憶させ、特定のキーワードを合図に、その作業を全自動で実行させる機能です。
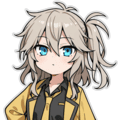
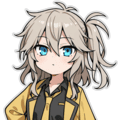
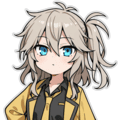
初回の設定や確認作業は必要です



「一度設定すれば、簡単な操作で自動化できます」とするのが適切かもですね
まずは一度だけ、AIと対話しながら、あなたの理想の作業プロセスを実演してみましょう。
- AIに作業を実演させる:
「今週のデイリーノートをすべて読み込んで。そして、内容を『今日のハイライト』『課題と解決策』『学び』の3つの見出しに再構成して。最後に、未完了のタスクだけをリストアップして、新しいノートにまとめて。」 - プロセスをルールとして記憶させる:
この一連の作業がうまく行ったら、AIにこう指示します。
「完璧な仕事でした。今実行した全プロセスを、『週末の週次レビュー』という名前のルールとして保存してください。」 - ワンクリックで実行:
AIが「指示書ファイル」を作成してくれます。次回以降は、あなたがAIチャットで「週末の週次レビューをお願い」と一言入力するだけで、AIがこの指示書を読み込み、面倒なレビュー作業を全自動で実行してくれます。
この「ルール機能」を使いこなすことは、あなたの優秀な分身を育てることに他なりません。一度やり方を教えれば、あとはあなたのために黙々と働いてくれます。
これにより、あなたは退屈な繰り返し作業から完全に解放されます。そして、その時間とエネルギーを、本当に価値のある、あなたにしかできない創造的な活動に集中させることができるようになるのです。
さあ、AIとの知的生産を始めよう


この記事で紹介したワークフローを、今日からあなたのものにするための最終ステップです。最小限の準備で第一歩を踏み出し、あなた自身の目的に合わせてカスタマイズしていくための具体的なヒントと、学びを継続するための情報源を紹介します。
前々からObsidianを使ってた古参としては鼻が高いよ…(cursol使ってAIにメモを探させるなんて考えたことなかったけど、ドヤ顔しとこ https://t.co/b5oV1EvOSF
— えいとびーと (@eightbeat8b) May 7, 2025
まずはこの構成から!最小構成のセットアップガイド
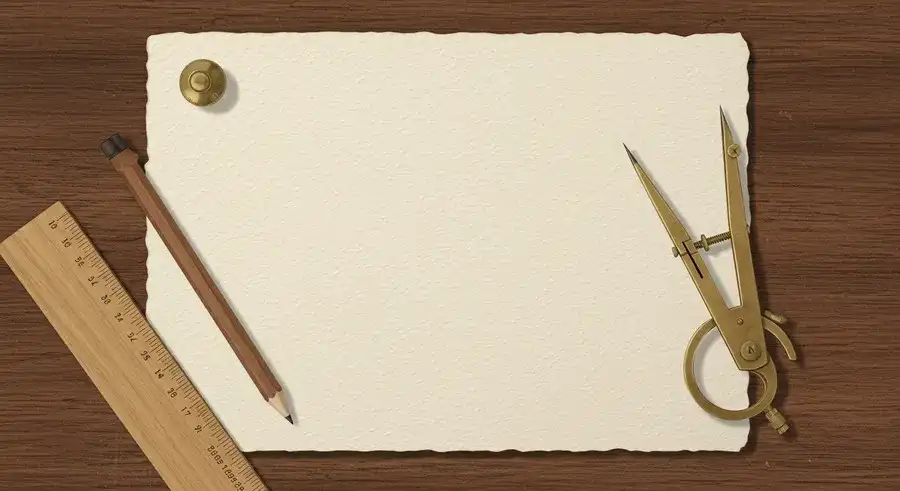
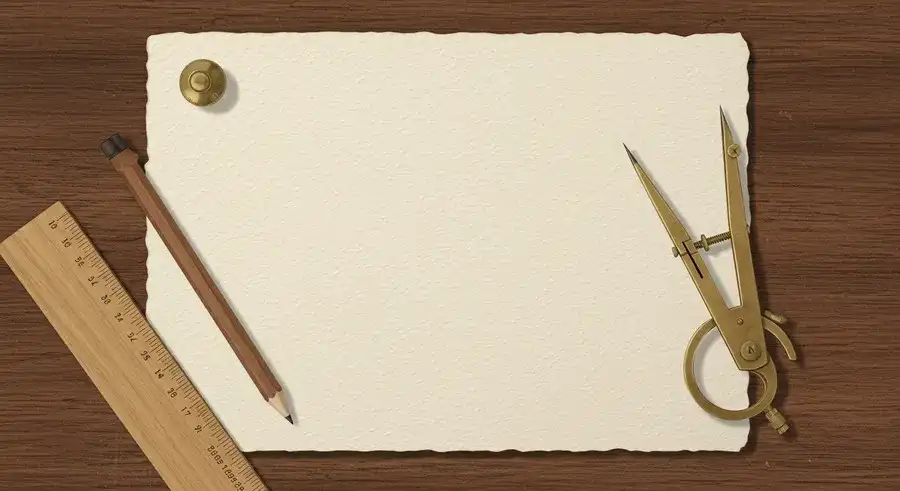
この記事を読んで、AIとの新しい知的生産の可能性にワクワクしている一方で、「自分に使いこなせるだろうか」「設定が多すぎて、どこから手をつけていいか分からない」と、少し不安になっているかもしれません。
その気持ちは、とても自然なことです。しかし、ご安心ください。最初から完璧なシステムを構築する必要は全くありません。大切なのは、まずAIとの「対話」を体験し、その面白さと可能性を肌で感じることです。
ここでは、そのための最もシンプルで、誰でも5分で始められるセットアップガイドをご紹介します。
ステップ1:Obsidianで「保管庫」を作る
まずはあなたの知識の家となる「保管庫(Vault)」を用意します。
- Obsidian公式サイトから、お使いのPCに合わせたアプリをダウンロードし、インストールしてください。
- Obsidianを起動し、「保管庫を新規作成」を選びます。
- 保管庫に好きな名前(例:「My_Second_Brain」)を付け、デスクトップなど分かりやすい場所に保存します。
これだけで、あなたの知識を安全に蓄えるための基盤が完成しました。
ステップ2:Cursorで「作業場」を開く
次に、AIアシスタントがいる「作業場」を用意し、先ほど作った保管庫を開きます。
- Cursor公式サイトからアプリをダウンロードし、インストールします。
- Cursorを起動し、「Open Folder…」という項目をクリックします。
- 先ほど作成したObsidianの保管庫フォルダ(例:「My_Second_Brain」)を選択して開きます。
これで、あなたの保管庫と作業場が接続されました。
ステップ3:AIに初めて話しかけてみる
さあ、いよいよAIとの対話です。Cursorの画面で新しいファイルを作成し、AIチャット(Cmd/Ctrl + K)を開いて、こう話しかけてみてください。
「こんにちは!これからあなたと一緒に、知的生産を革命したいと思います。まずは自己紹介として、あなたが最も得意なことを3つ教えてください。」
この小さな一歩が、あなたの知的生産を根底から変える大きな革命の始まりです。完璧な仕組みは、AIと対話しながら、少しずつ一緒に作り上げていけばいいのです。
あなたの目的に合わせたカスタマイズのヒント
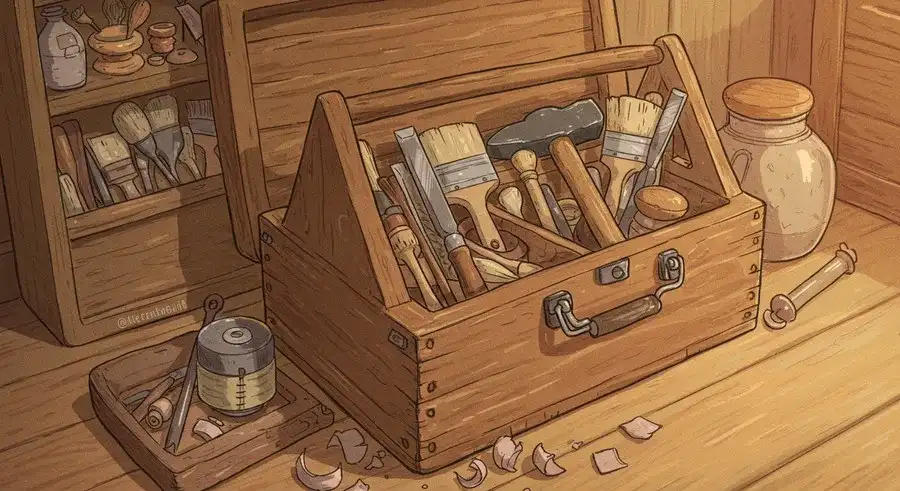
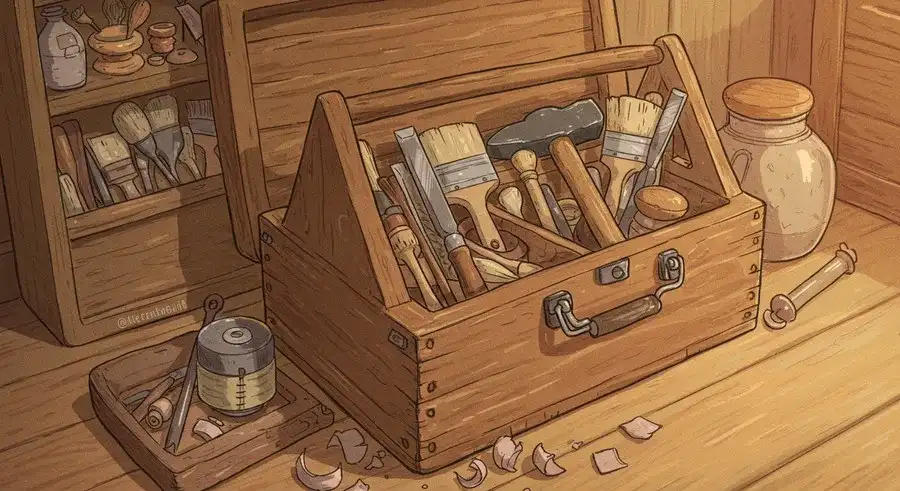
最小構成のセットアップが完了し、AIとの対話に少し慣れてきたら、次はこの強力なツールを、あなたの目的や仕事に合わせてカスタマイズしていきましょう。
人によって情報の扱い方や、解決したい課題は異なります。ここでは、3つの代表的な職種を例に、どのワークフローを重点的に活用すれば効果的か、カスタマイズのヒントをご紹介します。
Webライターやブロガーの方へ
▶︎ 重点フロー:フロー2「発想と執筆」
あなたの武器は、言葉を紡ぎ、読者の心を動かすことです。AIを、アイデアの壁打ち相手や優秀な編集者として活用しましょう。
- 活用シナリオ: 過去の記事や集めた資料をAIに読み込ませて新しい記事の「構成案」を作らせたり、「魔法のプロンプト」を使ってキャッチーなタイトルや導入文を複数提案させたりします。
- おすすめプラグイン: Templaterで記事の雛形を作成、Advanced TablesでMarkdownの表作成を効率化。
- フォルダ構成: 01_idea/ 02_draft/ 03_published/のように、執筆ステータスで管理するのがおすすめです。
開発者やエンジニアの方へ
▶︎ 重点フロー:フロー3「改善と自動化」
あなたは、複雑な問題を解決し、仕組みを構築するプロフェッショナルです。AIを、コーディングの相棒や面倒な作業を代行してくれるアシスタントとして使いこなしましょう。
- 活用シナリオ: コードのリファクタリングやテストコードの生成をAIに任せたり、「AIとの相談」でファイル整理や環境構築を自動化したりします。技術ドキュメントの作成も得意です。
- おすすめプラグイン: Obsidian Gitでのバージョン管理は必須。Dataviewでプロジェクトの進捗を可視化するのも強力です。
- フォルダ構成: projects/ snippets/ docs/のように、技術要素ごとに分類すると良いでしょう。
研究者や学生の方へ
▶︎ 重点フロー:フロー1「収集と構造化」
あなたは、膨大な情報の中から本質を見抜き、新たな知を創造する探求者です。AIを、大量の文献を読み解き、知識を体系化してくれるリサーチアシスタントとして活用してください。
- 活用シナリオ: Kindle HighlightsやZotero連携で集めた文献情報を、AIに「自動で要約」させ、重要なキーワードを抽出させます。複数の論文を読み込ませ、その共通点や相違点を分析させることも可能です。
- おすすめプラグイン: Citationsで参考文献の管理を効率化。Calendarで日々の研究記録を付けるのも有効です。
- フォルダ構成: Zettelkastenメソッドに基づき、LiteratureNote/(文献ノート)とPermanentNote/(恒久ノート)に分けるのが王道です。
これらのヒントを参考に、あなただけの最強のワークフローを構築していくプロセスそのものを、ぜひ楽しんでください。
一緒に学ぶコミュニティと更なる情報源


新しいツールの導入には、熱意と共にある種の「孤独」がつきまといます。「この設定で本当に合っているのだろうか」「もっと効率的な使い方があるのではないか」。そんな疑問を一人で抱え、試行錯誤を繰り返すうちに、いつしかモチベーションが薄れてしまい、結局元のやり方に戻ってしまった、という経験はありませんか。
どんなに強力なツールも、使い続けなければ意味がありません。そして、学びを継続させる最大の秘訣は、一人で悩み続けないことです。
幸いなことに、ObsidianとCursorの世界には、あなたと同じように知的生産の探求を楽しむ、多くの先駆者たちが存在します。彼らが築き上げた知のネットワークに加わることで、あなたの学びは加速し、何倍も楽しく、実りあるものになります。
一人で漕ぎ出す小舟から、多くの仲間と共に進む大きな船へ。さあ、コミュニティという名の海へ、次の航海に出ましょう。
リアルタイムの情報が集まる「X(旧Twitter)」
まずは、最も手軽に始められるX(旧Twitter)から情報収集を始めるのがおすすめです。
キーワード「Obsidian Cursor」や「#Obsidian」で検索すれば、世界中のユーザーが日々発見している新しい活用術や、便利なプラグインの情報、美しいカスタマイズ例などがリアルタイムで流れてきます。気になるユーザーをフォローし、その思考に触れるだけで、自分では思いつかなかったようなアイデアに出会えるでしょう。
先駆者たちの知恵が詰まった「ブログやnote」
より深く、体系的な知識を学びたいなら、先駆者たちが執筆したブログやnoteが最高の教科書になります。
この記事でも参考にさせていただいたように、多くのユーザーが自身の試行錯誤の過程や、具体的なワークフローを惜しみなく公開しています。彼らの記事を読むことは、いわば成功へのショートカットです。特に、非エンジニア向けの丁寧な解説記事や、特定の職種に特化した活用事例は、あなたの課題解決に直結するヒントの宝庫です。
企業の活用事例から学ぶ
個人の活用例だけでなく、企業がどのようにこれらのツールを活用しているかを知ることも、大きな刺激になります。
例えば、DeNA社が公式YouTubeチャンネルでObsidianの活用法を紹介している事例などがあります。チームでどのように知識を共有し、生産性を高めているのか。こうしたプロの現場での実践例は、あなたのワークフローを次のレベルへと引き上げるための、貴重なインスピレーションを与えてくれるはずです。
あなたが次にとるべきアクション
この記事を読み終えた今、あなたはAIとの知的生産革命のスタートラインに立っています。しかし、ゴールは一人で目指す必要はありません。
コミュニティに参加し、他者の知見を吸収し、そしていつかはあなた自身が誰かの道標となる。その循環こそが、知的生産の喜びを最大化させます。
さあ、まずはXでハッシュタグを検索することから、あなたの新しい冒険を始めてみませんか。
cursor & obsidian の使い方:この記事の要点まとめ
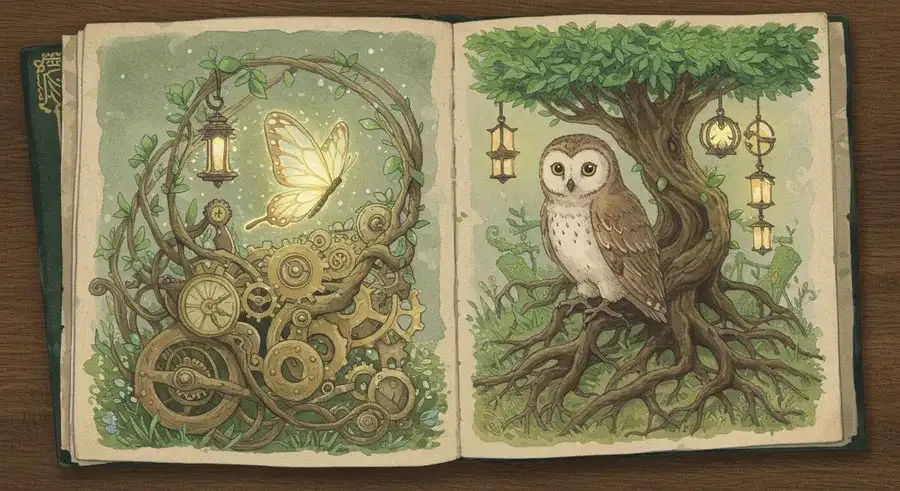
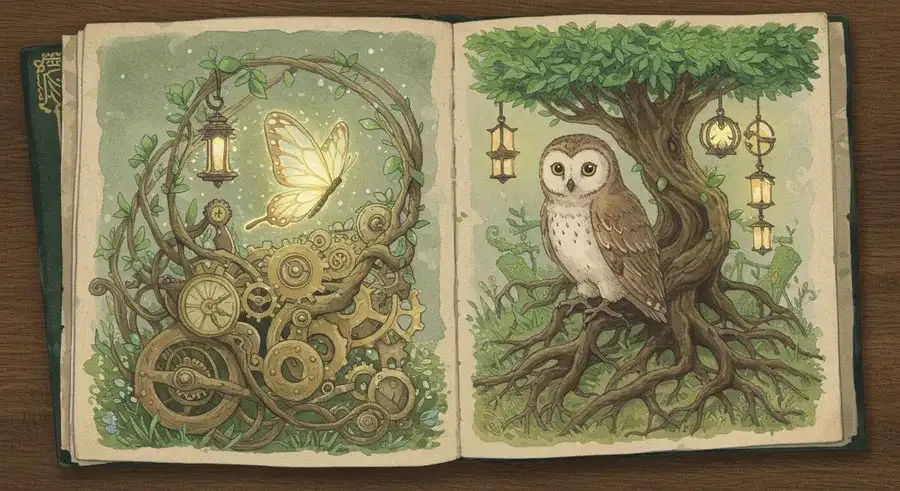
- Obsidianは「知識の保管庫」、Cursorは「AIとの実行環境」という役割分担が基本である
- 面倒なメモ整理をAIに任せ、人間はより創造的な「思考」に集中すべきである
- ローカル保存型のObsidianは、プライバシーを守りつつ将来のAI連携にも対応可能である
- 情報収集はWeb ClipperやKindle連携の活用で半自動化できる
- 集約した情報はAIに自動でタグ付けや要約をさせることが可能である
- GitHubを使ったPC・スマホ同期は、AIと対話しながらなら非エンジニアでも実現できる
- 複数ノートをAIに参照させ、質の高い記事構成案をゼロから作らせることができる
- AIに役割を与える「魔法のプロンプト」が、文章生成の質を大きく左右する
- ファイル名の一括変更など、面倒なファイル整理はAIに相談しながら安全に実行できる
- 「ルール機能」を使えば、週次レビューなどの定型作業をワンクリックで自動化可能である
- まずはObsidianとCursorのインストールという最小ステップから始めることが重要である
- WEBライターは「発想と執筆」のフローが特に有効である
- 開発者は「改善と自動化」のフローに注力すると良い
- 研究者や学生は「収集と構造化」のフローを最大限活用すべきである
- X(旧Twitter)や先駆者のブログなど、コミュニティから学ぶことで挫折しにくくなる
関連リンク
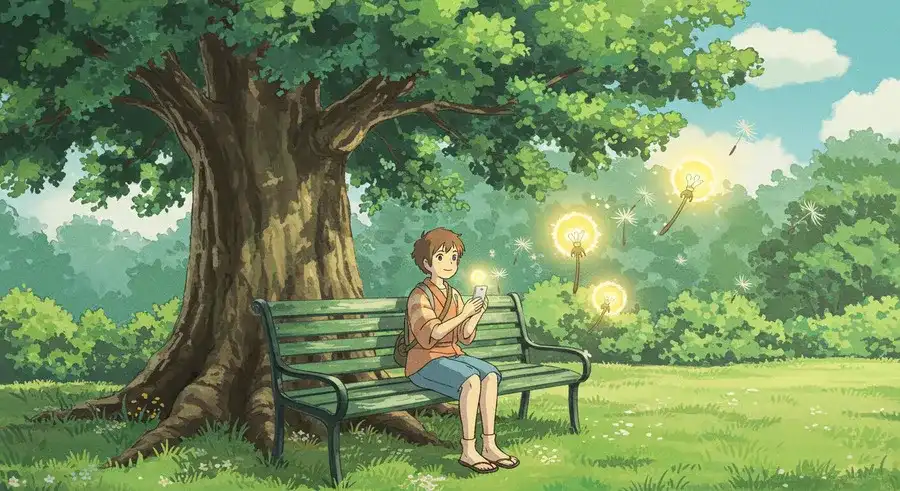
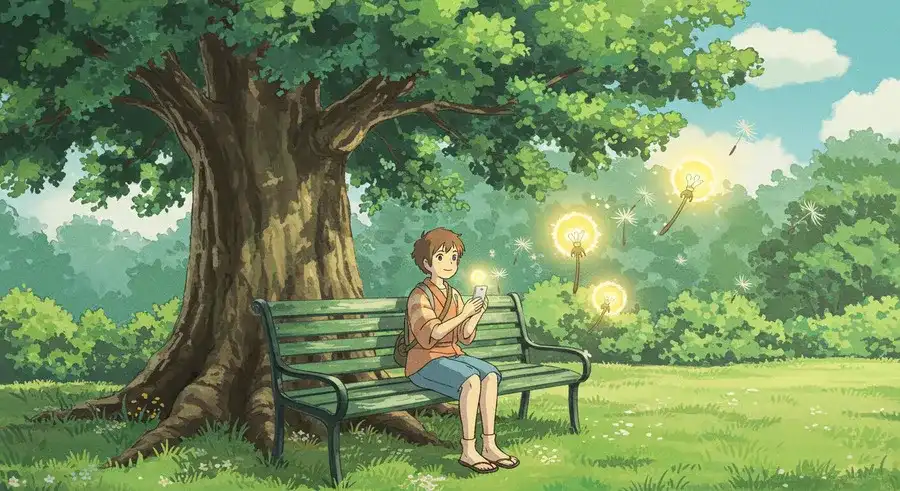
この記事で紹介したワークフローの背景にある思想や技術、そして社会的な文脈をより深く理解するために、信頼性の高い外部サイトへのリンクをご案内します。
Wikipedia – 「Zettelkasten」のページ
記事で紹介した「第二の脳」を構築する思想の源流には、「Zettelkasten(ツェッテルカステン)」という情報管理術があります。この手法の歴史や原則について、学術的な背景から詳しく知りたい方は、こちらのページをご参照ください。Obsidianが持つ思想の深さをより一層理解できます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ツェッテルカステン
OpenAI公式ブログ – GPT-4oの紹介やLLMに関する解説ページ
記事中で活躍するAI(LLM)の技術的な背景を知ることは、ツールのポテンシャルを最大限に引き出す上で役立ちます。Cursorなどが採用するAI技術の代表格、GPTシリーズの開発元であるOpenAIの公式ブログでは、最新のAI技術に関する最も正確な情報が公開されています。
https://openai.com/blog
MIT Technology Review (日本版) – 「生成AI」や「生産性」に関する特集・解説記事
この記事で提案したAIとのワークフローが、ビジネスや社会全体にどのようなインパクトを与えているのか。マクロな視点を知ることで、あなたの取り組みの重要性を再認識できるはずです。世界的な技術メディアであるMIT Technology Reviewでは、「生成AI」が働き方や生産性をどう変えていくかについての、質の高い論考が多数掲載されています。
https://www.technologyreview.jp/

コメント