「ブログで稼ぎたい!」そう思って一歩踏み出そうとした時、多くの初心者がぶつかる大きな壁、それがブログジャンルの決め方ですよね。「一体何を書けばいいの?」「どうせなら稼げるテーマを選びたいけど…」そんな悩みを抱えていませんか? 実は、この最初のジャンル選びでつまずき、努力が報われずに挫折してしまう人が後を絶ちません。なんと、その割合は9割にものぼると言われるほど、重要な分岐点なのです。
なぜ、これほどまでにブログジャンル選びは難しいのでしょうか? 無数にある選択肢、情報の洪水、「失敗したくない」というプレッシャー…。この記事では、そんな初心者特有の悩みに寄り添いながら、失敗しないブログジャンルの決め方を徹底解説します。「収益性の低い趣味ブログで時間を無駄にしてしまった…」「YMYLに手を出してアクセスが全く集まらなかった…」といった、先輩たちのリアルな失敗談も交えつつ、あなたが「稼げる土俵」を見つけるための具体的なステップを明らかにしていきます。
この記事を読み進めれば、単に「おすすめジャンル」を知るだけでなく、
- 収益性・市場規模・競合など、稼げるジャンルを見極める5つの明確な基準
- プログラミングや英会話がなぜ強いのか? 意外な穴場ジャンルの可能性
- 絶対に避けるべきYMYLや低承認率ジャンルの具体的な理由
- どうしても決められない時の**「ASP逆算法」や「30記事テスト」**といった実践的なテクニック
まで、体系的に理解できます。もうジャンル選びで悩み続けるのは終わりにしませんか? あなたのブログ成功への羅針盤となる情報が、ここにあります。さあ、一緒に「稼げるブログジャンル」を見つけ出す旅を始めましょう!
✅この記事を読むとわかること
- ブログジャンル選びで初心者が陥りやすい失敗パターンとその理由
- 収益性や市場規模など稼げるジャンルを見極めるための5つの判断基準
- YMYLや承認率の低いジャンルなど避けるべきテーマとその根拠
- ジャンル決定に迷った際のASP活用やネタ出しなどの具体的な解決策
ブログのジャンル選びはなぜ9割が失敗するのか?

「ブログで稼いでみたい」。そんな思いを胸に、意気揚々と情報収集を始める人は後を絶ちません。しかし、その最初の関門である「ジャンル選び」で、驚くほど多くの人が躓き、そして挫折していく現実があります。なぜ、ブログのジャンル選びはこれほどまでに難しく、そして失敗する人が多いのでしょうか? そこには、初心者ならではの思考の落とし穴と、ブログ収益化の構造的な問題が潜んでいるのです。今回は、その“失敗の本質”に迫ってみましょう。一体、どこで道を誤ってしまうのか。
なぜ初心者はジャンル選びに悩むのか?
ブログを始めようと思い立った時、多くの人が最初にぶつかる壁。それが「何について書くか」というテーマ、すなわちジャンル選びです。この段階で手が止まってしまう、あるいは延々と悩み続けてしまうのは、決してあなただけではありません。むしろ、ごく自然な反応と言えるでしょう。
その理由はいくつか考えられます。まず、選択肢が無限にあるように感じられること。インターネット上にはありとあらゆる情報が溢れており、「これも書けそう」「あれも面白そう」と目移りしてしまう。しかし、いざ一つに絞ろうとすると、「本当にこれでいいのか?」「もっと稼げるジャンルがあるのでは?」という不安が頭をもたげます。まるで、広大な海原に小舟で漕ぎ出すような心細さ。指針がない状態での選択は、誰にとっても難しいものです。
次に、「稼ぎたい」という気持ちと「書きたい」という気持ちのせめぎ合い。純粋に自分の好きなこと、情熱を傾けられることを書きたい。でも、どうせやるなら収益に繋げたい。この二つの欲求が、時として相反することがあります。好きなテーマが必ずしも稼げるジャンルとは限らない。逆に、稼げると言われるジャンルに全く興味が持てない。このジレンマが、決断を鈍らせる大きな要因となります。
さらに、情報の洪水による混乱も無視できません。「ブログで稼ぐならこのジャンルが鉄板!」「いや、そのジャンルはもうオワコンだ」といった、玉石混交の情報がネット上には飛び交っています。成功者の体験談、アフィリエイト会社の推奨ジャンル、インフルエンサーの発信…どれを信じればいいのか分からなくなり、かえって動けなくなってしまう。特に初心者は、経験がない分、外部の情報に振り回されやすい傾向があります。
そして、根底にあるのは「失敗したくない」という強い思いでしょう。ジャンル選びがブログ収益化の成否を大きく左右するという事実は、多くの発信者が語るところ。だからこそ、「最初の選択を間違えたら、かけた時間も労力も無駄になるのではないか」という恐怖心が先に立ち、完璧な選択をしようと力んでしまう。しかし、皮肉なことに、その完璧主義こそが、行動を妨げる最大の足かせとなるのです。
このように、選択肢の多さ、内面の葛藤、情報の氾濫、失敗への恐れといった複合的な要因が絡み合い、初心者をジャンル選びの迷宮へと誘い込みます。この最初のハードルを越えられないまま、ブログ開設を断念してしまう人も少なくないのが実情。まずは、悩むこと自体は当然なのだと受け入れるところから、始めてみるのが良いのかもしれません。
「やってみたけど稼げない」――多くの人がハマる典型パターン
悩み抜いた末、ようやくジャンルを決めてブログを書き始めた。あるいは、「考えるより行動だ!」と見切り発車でスタートした。しかし、数ヶ月、半年と続けても、一向に収益が上がらない…。これもまた、ブログ初心者が直面しがちな、あまりにも典型的な失敗パターンです。一体なぜ、努力が成果に結びつかないのでしょうか?
最も多いのが、「収益性の低いジャンル」を選んでしまったケースです。例えば、自分の趣味である映画レビューや読書感想、旅行記など。これらは確かに書きやすく、情熱も込めやすいかもしれません。しかし、紹介できるアフィリエイト広告の単価が低い、あるいは広告自体が少ない、という現実があります。Amazonや楽天のアフィリエイトは比較的取り組みやすいですが、書籍やDVDなどの紹介料率は数%程度。単価も数百円から千円程度のものが多く、1件売れたとしても数十円の報酬にしかなりません。月に数万円の収益を目指すには、膨大なアクセス数と販売数を達成する必要があり、これは初心者にとって極めてハードルが高いと言わざるを得ません。労力に見合ったリターンが得られず、モチベーションが枯渇してしまうのです。
次に、「市場が小さい、あるいは需要がニッチすぎる」ジャンル。自分の専門分野や、非常にマニアックな趣味について書く場合などがこれに当たります。確かに競合は少ないかもしれませんが、そもそもその情報を求めている人の絶対数が少なければ、いくら質の高い記事を書いてもアクセスは集まりません。ブログ収益の基本は「アクセス数 × 成約率 × 単価」。最初のアクセス数が確保できなければ、後の計算式は成り立たないのです。「検索ニーズのないジャンルでは、記事の品質や量にこだわっても全く意味がない」という厳しい現実を、後になって知ることになります。
また、「競合が強すぎるジャンル」に真正面から挑んでしまうパターンも散見されます。稼げると言われる人気ジャンルには、当然ながら企業メディアや経験豊富なアフィリエイターがひしめいています。彼らは豊富な資金力や組織力、SEOノウハウを駆使して、検索上位をがっちり固めていることが多い。初心者が個人ブログで、同じ土俵で戦いを挑んでも、なかなか太刀打ちできません。「このキーワードで上位表示できれば稼げるはず」と考えても、その上位表示自体が困難を極めるのです。結果として、誰にも読まれない記事を量産してしまうことになりかねません。
さらに、「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれる、お金や健康に深く関わるジャンルに、専門知識なく手を出してしまうケース。後述しますが、これらのジャンルはGoogleが特に品質を厳しく評価するため、権威性や信頼性の低い個人ブログが検索上位を獲得するのは非常に困難です。「専門家じゃないけど、体験談なら書ける」と思っても、なかなか評価されず、アクセスが集まらない。これも、よくある失敗の一つです。
そして、意外と見落としがちなのが「継続できない」こと。最初は意気込んでいても、興味のないジャンルを選んでしまったり、ネタがすぐに尽きてしまったりすると、記事更新が苦痛になります。ブログで成果が出るまでには、一般的に半年から1年はかかると言われます。その長期間、モチベーションを維持できずに挫折してしまう。これも立派な失敗パターンと言えるでしょう。
これらの典型パターンに共通するのは、「ジャンル選定時点での見通しの甘さ」です。収益構造、市場、競合、自身の適性といった要素を十分に検討しないままスタートしてしまうことで、後々「こんなはずじゃなかった」という壁にぶつかるのです。努力の方向性を間違えると、いくら頑張っても報われない。それがブログジャンル選びの怖さでもあります。
会話風コメント:実際に“遠回り”をしてしまった人のリアルな声
Aさん(30代・主婦): 「私、最初は子育てブログ始めたんですよ。日々の奮闘記とか、便利グッズの紹介とか。書くのは楽しかったんですけど、全然お金にならなくて。せいぜいAmazonアフィリで月数百円とか…。『これじゃパート代にもならないじゃん!』って気づいて(笑)。」
Bさん(20代・会社員): 「僕は、流行ってた仮想通貨ブログに飛びつきましたね。『億り人!』みたいなのに憧れて。でも、専門用語とか難しくて全然ついていけないし、何より競合サイトが強すぎて…。結局、ほとんどアクセスないままフェードアウトしちゃいました。もっと自分の詳しい分野でやればよかったって後悔してます。」
Cさん(40代・フリーランス): 「私の場合は、健康系のサプリメント紹介。当時はYMYLなんて言葉も知らなくて、『体験談書けば売れるでしょ』って安易に考えてたんです。最初は少し売れたんですけど、ある日突然Googleのアップデートで検索順位が圏外に…。それまで積み上げてきたものが一瞬でゼロになった感じで、本当にショックでしたね。ジャンル選びって、そういうリスクも考えないといけないんだなって痛感しました。」
Dさん(20代・学生): 「ゲームが好きだから、ゲームレビューブログなら続けられるかなって。確かに記事書くのは苦じゃなかったんですけど、紹介できる広告が少なくて。新作ゲームの紹介とかしても、発売日に情報が集中するだけで、安定したアクセスには繋がらないんですよね。もっと長期的に需要があるジャンルを選べばよかったかなぁ…。」
これらの声は、決して他人事ではありません。誰もが陥る可能性のある、リアルな失敗談です。彼らの経験から学ぶべきは、「好き」という気持ちだけでは乗り越えられない壁があること、そして、事前のリサーチと戦略がいかに重要か、ということではないでしょうか。では、どうすればこれらの失敗を避け、稼げるジャンルを見極めることができるのか? 次の章で、その具体的な基準を探っていきましょう。遠回りした彼らの声が、あなたの道標となるかもしれません。
稼げるジャンルを見極めるための5つの基準とは
ブログジャンル選びで失敗しないためには、闇雲に「好き」や「流行り」に飛びつくのではなく、明確な基準を持って判断することが不可欠です。まるで航海士が星を読むように、客観的な指標を頼りに進むべき道筋を見定めなければなりません。ここでは、ブログで収益を上げるために特に重要となる「5つの基準」を解説します。これらの基準を多角的に検討することで、より成功確率の高いジャンル選定が可能になるはずです。さて、あなたはこれらの基準を意識できているでしょうか?
基準①:収益性が高いか(単価・承認率・売れやすさ)
ブログで収益を上げることを目指す以上、まず最初に確認すべきなのが、そのジャンルの「収益性」です。どれだけ素晴らしい記事を書き、多くのアクセスを集めたとしても、収益性が低ければ努力は報われません。収益性は、主に以下の3つの要素で測ることができます。
- アフィリエイト報酬単価:
ブログ収益の柱となるのがアフィリエイト広告です。紹介した商品やサービスが成約するごとに報酬が発生しますが、この「1件あたりの報酬額(単価)」がジャンルによって大きく異なります。例えば、物販系のAmazonアソシエイトなどでは、商品価格の数%(数十円~数百円)が一般的ですが、金融(クレジットカード、証券口座開設など)、転職、美容(エステ、脱毛など)、通信(光回線、格安SIMなど)といったジャンルでは、1件あたり数千円から、場合によっては1万円を超える高単価な案件も存在します。「初心者はまず1件1000円以上を目安に」というアドバイスがありましたが、これは一つの指標として有効でしょう。報酬単価が低いと、同じ収益目標を達成するためには、より多くの成約数が必要になります。例えば、月5万円を稼ぐ場合、単価500円なら100件の成約が必要ですが、単価5,000円なら10件で済みます。どちらが現実的かは言うまでもありません。もちろん、「高単価=売れにくい」という側面もありますが、労力対効果を考えれば、ある程度の単価の高さは無視できない要素です。ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)に登録すれば、様々なジャンルの広告案件とその報酬単価を確認できます。A8.netやもしもアフィリエイトなどが代表的です。まずはこれらのASPに登録し、どんなジャンルに高単価案件が多いのかをリサーチすることから始めましょう。 - 承認率:
報酬単価と並んで重要なのが「承認率」です。アフィリエイトでは、広告経由で商品購入やサービス申し込み(成果発生)があっても、それが広告主によって「正当な成果」として承認されなければ、報酬は支払われません。この「発生した成果のうち、承認される割合」が承認率です。前述した章で指摘されているように、承認率が低いジャンルも存在します。例えば、資料請求や見積もり依頼(リフォーム、保険相談など)、無料カウンセリング予約(エステ、美容外科など)、クレジットカード発行などは、その後のキャンセルや審査落ちなどにより、成果が承認されないケースが比較的多い傾向にあります。せっかく10万円分の成果が発生しても、承認率が20%であれば、実際に受け取れる報酬は2万円になってしまいます。承認率はASPの管理画面で確認できる場合もありますが、非公開の場合も多いです。可能であれば、事前にASPの担当者に問い合わせたり、経験者の情報を集めたりして、極端に承認率が低いジャンルは避けるのが賢明です。 - 売れやすさ(成約率・知名度):
単価が高く、承認率も問題なくても、そもそも商品やサービスが「売れやすい」ものでなければ意味がありません。売れやすさは、市場での需要や商品の魅力、そして「知名度」に左右されます。一般的に「知名度が高い方が断然売りやすい」と強調されています。CMなどでよく見かける有名な商品やサービスは、既に多くの人が認知しており、安心感もあります。全く無名の商品をブログだけで認知させ、購買まで繋げるのは至難の業です。「ブログの役割は商品の認知度を上げることではなく、その商品を必要としている人に届けること」という視点は、特に初心者にとって重要です。ライバルが多いことを恐れるよりも、既に市場で受け入れられている商材を選ぶ方が、成果には繋がりやすいでしょう。もちろん、成約率は記事の質やターゲット設定にも大きく依存しますが、そもそもの商材パワーも無視できません。ASPで案件を探す際には、「この商品は自分でも欲しいと思うか?」「周りの人に勧められるか?」といった視点も持つと良いでしょう。
これらの「単価」「承認率」「売れやすさ」を総合的に評価し、収益化のポテンシャルが高いジャンルを見極めることが、稼げるブログへの第一歩となります。
基準②:市場規模と将来性はあるか
次に検討すべきは、そのジャンルの「市場規模」と「将来性」です。いくら収益性が高くても、そもそもそのジャンルにお金を払う人が少なかったり、今後市場が縮小していくようでは、長期的なブログ運営は難しくなります。
市場規模とは、そのジャンルに関心を持ち、商品やサービスを購入する可能性のある潜在的なユーザーの数、あるいはその市場で動いているお金の総額と捉えることができます。市場規模が大きいジャンルには、以下のようなメリットがあります。
- 多くのアクセスを集めやすい: ニーズを持つ人の絶対数が多いため、適切なキーワード選定とコンテンツ作成ができれば、大きなアクセス流入が期待できます。
- 多様な切り口が存在する: ユーザー層が広いため、「初心者向け」「女性向け」「〇〇な悩みを持つ人向け」など、ターゲットを絞った様々な切り口でコンテンツを展開できます。
- 競合が多くても共存の余地がある: パイが大きい分、複数のブログやサイトがそれぞれの得意分野でユーザーを獲得し、共存できる可能性があります。
逆に、市場規模が小さいニッチなジャンルでは、競合が少なくても獲得できるアクセス数に限界があり、ブログの成長も頭打ちになりがちです。
市場規模を調べるには、「(ジャンル名)+ 市場規模」といったキーワードで検索し、官公庁や調査会社のレポートなどを参考にする方法があります。また、無料ツールの「Google トレンド」を使って、関連キーワードの検索需要の推移を調べるのも有効です。検索数が長期的に安定しているか、増加傾向にあるかを確認しましょう。
将来性も重要な観点です。一時的なブームに乗ったジャンルは、瞬間的に大きなアクセスを集められても、ブームが去ると急速に関心が失われ、アクセスも激減するリスクがあります。例えば、一時期流行した特定の健康法や、瞬間的に話題になったアプリなどは注意が必要です。
一方で、今後も社会的なニーズの高まりが予想されるジャンルは、長期的に安定したアクセスと収益が期待できます。例えば、
- 高齢化社会関連: 健康、介護、終活など
- 働き方の多様化: 副業、転職、フリーランス支援、リスキリングなど
- 技術革新: AI、プログラミング、オンラインサービス(英会話、フィットネスなど)
- 環境意識の高まり: SDGs、エコ、サステナブル関連など
これらの分野は、今後も市場の成長が見込まれるため、将来性が高いと言えるでしょう。前述した章で挙げられている「英会話学習」「メンズコスメ」「プログラミング学習」なども、こうした時代の流れに乗ったジャンルと言えます。
もちろん、将来有望なジャンルにはライバルも多く参入してきます。しかし、大きな魚がたくさんいる海域で釣りをすることのメリットは計り知れません。短期的な視点だけでなく、5年後、10年後も需要があり続けるか、という長期的な視点で市場を見極めることが重要です。
基準③:競合に勝てる“切り口”はあるか
収益性が高く、市場規模も大きい。そんな魅力的なジャンルには、当然ながら多くの競合サイトが存在します。特に、企業が運営する大規模メディアや、経験豊富なベテランアフィリエイターがひしめく激戦区では、初心者が真正面から戦いを挑んでも勝ち目はありません。そこで重要になるのが、「競合に勝てる“切り口”」を見つけ出すことです。
これは、いわゆる「ポジショニング戦略」に近い考え方です。競合と同じ土俵で戦うのではなく、少しズラした独自の立ち位置を見つけることで、活路を開くのです。具体的には、以下のような視点が考えられます。
- ターゲットを絞り込む:
競合サイトが幅広い層をターゲットにしている場合、より特定の属性や悩みを持つ層に特化することで差別化を図ります。- 例:「転職」ジャンル → 「30代・未経験からのIT転職」「地方在住者のための転職」「育児と両立したいママの転職」
- 例:「英会話」ジャンル → 「ビジネス英語プレゼン特化」「海外旅行で使える日常会話フレーズ集」「TOEIC500点台からのスコアアップ法」
- 特定のテーマに深掘りする:
競合サイトが広く浅く情報を扱っている場合、ある特定のテーマについて、誰よりも詳しく、深く掘り下げたコンテンツを提供します。- 例:「プログラミング」ジャンル → 「Pythonを使ったデータ分析専門ブログ」「WordPressテーマ開発に特化」
- 例:「マッチングアプリ」ジャンル → 「特定のアプリの徹底攻略ブログ」「メッセージ術・デート術に特化」
- 独自の視点や経験を打ち出す:
他のサイトにはない、自分ならではの経験、知識、価値観を前面に出して、オリジナリティを確立します。「自分の実体験を元にテーマを決める」というアドバイスは、まさにこの点です。- 例:元人事担当者が語る転職成功の秘訣、浪費家だった筆者が実践した節約術、特定の持病を持つ人のための健康情報(※YMYL注意)
- 新しいキーワードやトレンドを狙う:
競合がまだ注目していない、新しいサービス、商品、技術、あるいは検索され始めたばかりのキーワード(ロングテールキーワード)を積極的に取り上げます。「仮想通貨」ジャンルのように、新しい用語やトレンドが出やすい分野では、後発でもチャンスがあります。また、「新着案件を狙う」という戦略もこれに近いでしょう。
競合サイトを分析することは非常に重要です。「ライバルをチラ見!」する程度で良いと述べられていますが、本格的にジャンルを決める段階では、もう少し踏み込んだ分析が必要になるでしょう。Googleで関連キーワードを検索し、上位表示されているサイトが、
- 誰(企業か個人か)が運営しているか?
- どんなターゲットに向けて?
- どんな切り口で?
- どんなコンテンツ(記事の質・量・網羅性)を提供しているか?
などを調査します。そして、「この競合がカバーできていない領域はどこか?」「自分ならどんな価値を提供できるか?」を考え抜くのです。
ただし、ここで注意したいのは、「誰もいない場所=必ずしも美味しい場所ではない」ということです。競合が全くいないということは、そもそも需要がない、あるいは収益化が難しいジャンルである可能性も高いのです(「成功例がないジャンルはおすすめできない」)。あくまで、「強い競合がいる中で、自分が勝てる(あるいは棲み分けできる)ポジションを見つける」という視点が重要になります。
この「切り口」探しは、ジャンル選びの中でも特に創造性が求められる部分です。市場と競合を分析し、自分自身の強みを掛け合わせることで、独自の戦い方を見つけ出す。それが、後発でも成功するための鍵となります。
基準④:持続性と安定アクセスは見込めるか
ブログ運営は短距離走ではなく、マラソンです。一時的にアクセスが急増しても、それが長続きしなければ安定した収益には繋がりません。そのため、選ぶジャンルが「持続性」を持ち、長期的に安定したアクセスが見込めるかどうかも重要な判断基準となります。
ここで言う「持続性」とは、そのジャンルへの関心が一時的なブームで終わらず、長期間にわたって安定していることを指します。
- 流行り廃りの激しいジャンル:
特定の芸能人のスキャンダル、瞬間的に話題になったゲームやアプリ、テレビで紹介された健康法などは、瞬間風速的に大きなアクセスを集めることがあります。しかし、人々の関心はすぐに移ろい、数週間後、数ヶ月後にはほとんど検索されなくなるケースが少なくありません。こうしたジャンルに依存していると、常に新しいトレンドを追いかけ続けなければならず、安定したブログ運営は困難です。 - 安定的・普遍的な需要があるジャンル:
一方で、人間の根源的な欲求や悩みに関連するジャンルは、時代が変わっても需要がなくなることはありません。- 人間関係: 恋愛、結婚、子育て、コミュニケーション
- 仕事・お金: 転職、副業、節約、投資(※YMYL注意)
- 健康・美容: ダイエット、スキンケア、筋トレ(※YMYL注意)
- 学習・スキルアップ: 英語、プログラミング、資格取得
- 趣味・娯楽(定番系): 料理、旅行、アウトドア、ペット
これらのジャンルは、常に一定数の人々が情報を求めているため、長期的に安定したアクセスが見込めます。「結婚・マッチングアプリ」「転職サービス」「プログラミングスクール」「オンライン英会話」「パーソナルジム」などは、まさにこうした普遍的なニーズに応えるジャンルと言えるでしょう。
ただし、安定ジャンルには当然ながら競合も多く、常に新しい情報やサービスが登場するため、継続的な情報収集とコンテンツの更新は不可欠です。それでも、一度ブログの基盤を築けば、比較的安定したアクセスと収益を得やすいのが大きなメリットです。
また、「季節性」も考慮に入れると良いでしょう。例えば、「夏休みの自由研究」「クリスマスのプレゼント選び」「確定申告のやり方」などは、特定の時期にアクセスが集中しますが、それ以外の時期は閑散としがちです。季節性の高いテーマだけを扱うのではなく、年間を通じて安定したアクセスが見込めるテーマと組み合わせるなどの工夫が必要になります。
Google トレンドでキーワードの検索需要の推移を確認する際も、短期的なスパイク(急上昇)だけでなく、年単位での長期的なトレンドや季節変動のパターンを把握することが重要です。
ブログは、一度作ったら終わりではありません。継続的に情報を発信し、読者との関係を築いていくストック型のメディアです。だからこそ、一過性の花火で終わらない、持続可能なジャンルを選ぶ視点が欠かせないのです。
基準⑤:自分の適性・経験とリンクしているか
これまで挙げてきた4つの基準(収益性、市場規模、競合、持続性)は、主に市場や外部環境を分析する客観的な視点でした。しかし、最後の5つ目の基準は、あなた自身の内面に関わる、非常に重要な要素です。それは、「そのジャンルが、自分自身の興味・関心、知識・経験、あるいは情熱とリンクしているか?」という点です。
なぜこれが重要なのでしょうか? いくら稼げる可能性が高く、市場も有望で、競合にも勝てそうなジャンルであっても、あなた自身がそのテーマに対して全く興味を持てなかったり、知識を深めることに苦痛を感じたりするようでは、ブログ運営を長期間続けることは極めて困難だからです。
「興味関心があるジャンルを選ぶ」「専門性を発揮しやすいジャンルを選ぶ」ことの重要性が強調されています。また、「自身の適性」として、興味関心や学習意欲が挙げられています。
- 興味・関心・情熱:
ブログ運営は、地道な作業の連続です。キーワード選定、構成案作成、記事執筆、画像選定、推敲、投稿、分析、リライト…。成果が出るまでには時間がかかり、モチベーションの維持が大きな課題となります。自分が心から興味を持てるジャンルであれば、情報収集も楽しく、記事を書くことも苦になりにくいでしょう。「WordPressって面白そう」という興味から始めたという、「かずよし氏」のように、”好き”や”面白い”という感情は、継続の大きな原動力となります。逆に、全く興味のないジャンルについて、お金のためだけに書き続けるのは精神的に辛いものです。 - 知識・経験・スキル:
既に持っている知識や経験、仕事で培ったスキルを活かせるジャンルを選ぶことは、大きなアドバンテージになります。- 質の高い記事を書きやすい: 専門的な知識や実体験に基づいた記事は、具体性や説得力が増し、読者からの信頼を得やすくなります。Googleが重視するE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の観点からも有利です。
- 情報収集が効率的: 既にある程度の知識ベースがあるため、新しい情報をインプットする際も理解が早く、効率的に学習を進められます。
- オリジナリティを出しやすい: 他の誰にも書けない、あなたならではの視点や体験談を盛り込むことで、競合との差別化が図りやすくなります。
もちろん、「今は詳しくなくても、これから勉強したい!」という強い意欲があれば、未経験のジャンルに挑戦することも可能です。しかし、その場合は、学習と記事作成を並行して進める必要があり、相応の覚悟と努力が求められます。挫折のリスクも高まることは認識しておくべきでしょう。
理想的なのは、客観的な基準(収益性、市場、競合、持続性)と、主観的な基準(自身の適性・経験)が高いレベルで合致するジャンルを見つけることです。しかし、完璧に合致するジャンルがすぐに見つかるとは限りません。その場合は、ある程度の妥協やバランス感覚も必要になってきます。
最終的にブログを書き、育てていくのは、他の誰でもないあなた自身です。自分の心と向き合い、「これなら続けられそうだ」「この分野なら貢献できそうだ」と思えるジャンルを選ぶこと。それが、長期的な成功への最も確かな道筋なのかもしれません。
コメント考察:初心者が気づかない“収益化のワナ”とは?
ライター考察: これら5つの基準を見ていくと、初心者が陥りやすい“収益化のワナ”がいくつか浮かび上がってきますね。
ワナ①:単価至上主義の罠
「とにかく稼ぎたい!」という気持ちが先行すると、ASPで報酬単価の高い案件ばかりに目が行きがちです。1件1万円!なんて見ると、「これだ!」と思ってしまう。しかし、単価が高い案件は、それだけ成約のハードルが高かったり、承認率が低かったり、あるいは強大な競合がひしめいていたりするケースが多い。単価という一点だけで判断してしまうと、結局「発生すれども承認されず」とか「そもそも全く売れない」といった事態に陥りかねません。報酬画面の数字に踊らされず、承認率や売れやすさ、競合状況を冷静に見極める視点が欠けていると、このワナにハマります。
ワナ②:市場規模の誤解
「市場が大きい方が稼げる」というのは真実ですが、それを鵜呑みにして、何の戦略もなく巨大市場に飛び込むのも危険です。例えば「ダイエット」や「クレジットカード」のような超巨大市場。確かにパイは大きいですが、その分、プロ中のプロが凌ぎを削っています。初心者が太刀打ちできる隙間はなかなか見つからない。市場規模の大きさに目を奪われ、競合分析や自身の強みを活かせる「切り口」探しを怠ると、大海に放り出された木の葉のように、ただただ翻弄されて終わってしまいます。「大きい=簡単」ではない、ということを理解する必要があります。
ワナ③:「好き」だけでは食えない現実
「好きなことを書いて稼げるなんて最高!」…理想ですが、現実はそう甘くありません。基準⑤で「適性」の重要性を説きましたが、それだけで他の基準を無視していいわけではない。どんなに情熱を込めて素晴らしい記事を書いても、収益化の導線(適切な広告案件)がなかったり、そもそも検索需要がなければ、自己満足で終わってしまいます。趣味ブログが悪いわけではありませんが、「稼ぐ」ことを目指すなら、「好き」という気持ちと、「稼げる構造」を両立させる、あるいはどこかで折り合いをつける冷静さが必要です。「好き」を優先しすぎて、収益性を度外視してしまうのは、典型的な初心者の失敗パターンかもしれません。
ワナ④:短期的な視点
「早く成果を出したい」という焦りから、瞬間的に話題になっているトレンドジャンルに飛びついたり、すぐに結果が出そうな(ように見える)手法に手を出したりする。しかし、ブログは本来、時間をかけて価値を積み上げていくもの。短期的なアクセスや収益に一喜一憂していると、持続性のあるジャンル選びや、長期的な視点でのコンテンツ作りがおろそかになりがちです。目先の利益にとらわれず、腰を据えて取り組めるジャンルか、長期的に価値を提供し続けられるか、という視点が抜けていると、結局は長続きしません。
これらのワナは、経験者から見れば「当たり前」のことかもしれません。しかし、初めてブログに取り組む初心者にとっては、なかなか気づきにくい落とし穴なのです。5つの基準を常に意識し、バランスの取れた判断を心がけること。それが、これらのワナを回避し、着実に成果へと繋げる道となるでしょう。次章では、これらの基準を踏まえた上で、今注目すべき具体的なおすすめジャンルを見ていきます。
今から始めても間に合う!注目のおすすめジャンル10選
「結局のところ、どのジャンルを選べばいいんだ?」 5つの基準を理解したところで、多くの人が抱くのはこの疑問でしょう。理論は分かった、でも具体的な候補が知りたい。そんな声に応えるべく、ここでは、インプットした情報に基づき、現在注目されている、あるいは今後も安定した需要が見込める「おすすめジャンル」を10個ピックアップしてご紹介します。
もちろん、これが絶対の正解ではありません。しかし、あなたのジャンル選びのヒントになる可能性は十分にあります。さあ、未来の収益源となるかもしれない、注目の市場を覗いてみましょう。
定番ジャンルと“伸びしろジャンル”の違いとは?
おすすめジャンルを紹介する前に、少しだけジャンルの性質について触れておきましょう。ブログで扱われるジャンルは、大きく「定番ジャンル」と「伸びしろジャンル」に分けられると考えられます。
定番ジャンルとは、長年にわたって安定した需要があり、市場がある程度成熟している分野を指します。データで挙げられているもので言えば、
- 転職サービス: 景気変動の影響は受けつつも、キャリアアップや働き方改革の流れで常にニーズがある。
- 結婚・マッチングアプリ: 婚活市場は安定しており、出会いの手段として定着。
- オンライン英会話: グローバル化や自己投資の意識の高まりから、根強い人気。
- パーソナルジム/スポーツジム: 健康志向、ダイエット需要は不変。
- VOD(動画配信サービス): 生活インフラの一部となりつつあり、安定市場に。
- 通信サービス(光回線など): 生活必需品であり、乗り換え需要も常にある。
これらのジャンルは、市場規模が大きく、収益性の高い広告案件も豊富に存在する傾向があります。まさに「王道」と言えるでしょう。しかし、その反面、競合が非常に多く、強力な企業メディアや古参アフィリエイターがひしめいている激戦区でもあります。初心者が参入するには、前述したような明確な「切り口」や「差別化戦略」が不可欠です。ただ漠然と情報をまとめるだけでは、まず埋もれてしまうでしょう。安定しているが故に、参入障壁は高い、とも言えます。
一方、伸びしろジャンルとは、比較的新しい市場であったり、近年になって急速に需要が高まっていたりする分野です。データで触れられているものでは、
- プログラミングスクール: IT人材需要の高まり、リスキリングの流れで急成長。
- メンズコスメ: 男性美容市場の拡大。まだ黎明期とも言える。
- 電子コミック(特にウェブトゥーンなど): スマホでの閲覧増加、新しい形態の登場。
- 副業: 働き方の多様化、収入源確保の意識向上。
- 仮想通貨: 技術や法整備の進展、新たな投資対象として(ただし変動は激しい)。
これらのジャンルは、市場がまだ発展途上であったり、新しいトレンドが次々と生まれていたりするため、後発でも先行者利益を得られるチャンスが残されています。競合も定番ジャンルほどには成熟しておらず、「新しい切り口」を見つけやすい可能性も。また、最新情報を追いかけることで、権威性を構築しやすい側面もあります。
ただし、デメリットとしては、市場がまだ不安定であったり、将来性が不透明であったりするリスクが挙げられます。ブームが去れば一気に需要がしぼむ可能性も否定できません。また、新しいジャンルであるが故に、収益化の方法(広告案件など)がまだ確立されていない、あるいは単価が低いといったケースもあります。
どちらが良い悪いという話ではありません。定番ジャンルで確実性を狙うか、伸びしろジャンルでチャンスを掴むか。それは、あなた自身の戦略やリスク許容度、そして何より「どの分野に情熱を傾けられるか」によって決めるべきでしょう。理想は、定番ジャンルの安定性と、伸びしろジャンルの将来性を併せ持つような領域を見つけることかもしれません。
では、具体的に、おすすめとして挙げられているジャンルは、どのような理由で注目されているのでしょうか?
プログラミング・英会話・スポーツジムはなぜ強い?
推奨ジャンルとして挙げられている「プログラミングスクール」「オンライン英会話」「パーソナルジム(スポーツジム)」。これらは、なぜブログジャンルとして「強い」のでしょうか? その背景には、現代社会のニーズと、アフィリエイト収益構造上の利点が深く関わっています。
1. プログラミングスクール:
- 圧倒的な需要の高さ: デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、ITスキルを持つ人材の需要は業界を問わず高まる一方です。エンジニア不足は深刻であり、プログラミングを学びたい、スキルアップしたいというニーズは非常に強い。リスキリングや副業として注目されていることも、需要を後押ししています。
- 高額なサービスと高単価アフィリエイト: プログラミングスクールの受講料は、数十万円単位になることが一般的です。サービスが高額であるため、紹介するアフィリエイトの報酬単価も1件あたり数万円といった高額なものが多く存在します。少ない成約数でも大きな収益に繋がりやすい構造です。
- 継続的な学習ニーズ: プログラミングは一度学んだら終わりではなく、常に新しい技術が登場します。そのため、初学者向けのスクール紹介だけでなく、中級者向けの学習法、特定の言語や分野に特化した情報など、継続的にコンテンツを提供できる深さがあります。
- 自身の経験を活かしやすい: エンジニア経験者であれば、その知識や体験談は非常に価値の高いコンテンツになります。未経験者でも、学習過程を発信することで、同じ悩みを持つ読者の共感を得ることができます。
2. オンライン英会話:
- グローバル化と根強い英語学習熱: ビジネスシーンでの必要性、海外旅行、趣味、子供の教育など、英語を学びたい理由は多岐にわたり、その需要は安定しています。特にオンライン英会話は、時間や場所に縛られず手軽に始められるため、コロナ禍以降さらに人気が高まりました。
- 多様なサービスと切り口: 日常会話、ビジネス英語、TOEIC対策、子供向けなど、様々な目的やレベルに応じたオンライン英会話サービスが存在します。そのため、「〇〇な目的の人におすすめのオンライン英会話比較」「レベル別・失敗しない選び方」「無料体験レッスンの活用法」など、多様な切り口で記事を作成できます。
- 継続課金モデルと安定収益: オンライン英会話は月額課金制のサービスが多く、一度入会すると長期間利用するユーザーも少なくありません。アフィリエイト報酬も、無料体験登録だけで発生するものや、月額料金の一部が継続的に支払われるものなどがあり、安定した収益に繋がりやすい可能性があります。
- 市場の成長性: 今後もグローバル化の流れは続くと予想され、英語学習市場、特にオンラインサービスの市場はさらに拡大していく可能性が高いと考えられます。
3. パーソナルジム / スポーツジム:
- 健康・美容への関心の高まり: 健康寿命の延伸、見た目への意識向上などから、フィットネスやトレーニングへの関心は年々高まっています。特にダイエットやボディメイクは、多くの人にとって普遍的なテーマです。
- パーソナルジムの付加価値: マンツーマン指導による効果の高さ、プライベートな空間、食事指導など、従来のスポーツジムにはない付加価値を提供するパーソナルジムの人気が高まっています。高価格帯のサービスが多いため、アフィリエイト報酬も比較的高めに設定されている傾向があります。
- 多様化するジムの形態: 24時間営業の無人ジム、女性専用ジム、特定のトレーニング(クロスフィット、ヨガなど)に特化したジムなど、ニーズの多様化に合わせて様々な形態のジムが登場しています。これにより、「地域別おすすめジム」「目的別(ダイエット、筋力アップなど)ジム比較」「初心者向けジムの選び方」といった切り口でコンテンツを作成できます。
- 体験談の価値が高い: 実際にジムに通った経験や、トレーニングの成果などを具体的に書くことで、読者の共感を呼び、説得力のあるコンテンツになります。ビフォーアフターなどを視覚的に示すことも効果的です。
これらのジャンルに共通するのは、「明確な悩みや目標を持ったユーザーが多いこと」「比較検討されることが多いサービスであること」「比較的高単価なアフィリエイト案件が存在すること」です。だからこそ、ブログでの情報発信がユーザーの意思決定に繋がりやすく、収益化しやすい「強い」ジャンルとなっているのです。
意外とブルーオーシャン?電子コミック・副業系の可能性
定番ジャンルや、需要が明確なスキルアップ系ジャンルに注目が集まりがちですが、「電子コミック」や「副業」といったジャンルもおすすめとして挙げられています。これらは一見すると競合が多そうに見えますが、視点を変えれば、まだ開拓の余地がある「ブルーオーシャン」的な側面も持っているのかもしれません。
1. 電子コミック:
- 市場の急拡大: スマートフォンの普及に伴い、電子書籍市場、特に電子コミック市場は急速に拡大しています。いつでもどこでも手軽に読める利便性から、紙媒体からの移行も進んでいます。
- ウェブトゥーンなど新しい波: 韓国発の縦読みフルカラー漫画「ウェブトゥーン」が世界的に人気を集めており、日本国内でも多くのプラットフォームが登場しています。こうした新しいフォーマットやプラットフォームに特化することで、先行者利益を得られる可能性があります。
- 多様な切り口: 特定のジャンル(異世界転生、恋愛、BLなど)のレビューやおすすめ、特定の電子書籍ストアの比較(セール情報、使い勝手など)、話題の新作紹介、隠れた名作の発掘など、切り口は多岐にわたります。
- 低単価だが成約しやすい?: 書籍のアフィリエイト単価は一般的に低いですが、漫画は比較的気軽に購入されやすい商材とも言えます。無料試し読みから有料会員登録へ繋げる、といった導線も考えられます。VOD(動画配信サービス)と組み合わせ、原作漫画とアニメ・ドラマをセットで紹介するなどの展開も可能です。
- 注意点: 競合は多い(特に大手レビューサイトやまとめサイト)。著作権に配慮した画像利用が必要。単価の低さをカバーする戦略(量、あるいは高単価ジャンルとの組み合わせ)が求められる。
2. 副業:
- 時代の要請: 終身雇用の崩壊、物価上昇、働き方改革などを背景に、「副業」への関心は爆発的に高まっています。「収入の柱を増やしたい」「スキルを活かしたい」「将来に備えたい」というニーズは非常に強い。
- テーマの広範さ: 副業と一口に言っても、ブログ、アフィリエイト、Webライター、動画編集、プログラミング、せどり、ハンドメイド販売、スキルシェア、投資、ポイ活…など、その種類は無数にあります。この広範さ故に、特定の副業に特化したり、複数の副業を組み合わせたり、あるいは「主婦向け」「会社員向け」「スキルなしから始められる」といったターゲットを絞ったりすることで、独自のポジションを築きやすいと言えます。
- 体験談が武器になる: 自身が実践している副業の体験談、成功例、失敗談、具体的なノウハウは、読者にとって非常に価値のある情報となります。信頼性を高め、ファンを作りやすいジャンルとも言えます。
- 多様な収益化: アフィリエイト(教材、ツール、サービス紹介)、アドセンス、自身のスキルや知識をまとめた情報商材の販売、コンサルティングなど、収益化の手段も多様です。
- 注意点: 競合ブロガーや情報発信者が非常に多い。玉石混交の情報が溢れており、信頼性の低い情報や詐欺的な情報も紛れているため、誠実な情報発信が求められる。「簡単に稼げる」といった安易な訴求は避けるべき。YMYL(投資など)に触れる場合は特に注意が必要。
これらのジャンルは、市場の大きさやトレンド性から見ると非常に魅力的です。しかし、その分、多くのプレイヤーが参入しており、単純な情報発信だけでは埋もれてしまう可能性も高い。成功の鍵は、やはり「独自の切り口」を見つけ、読者にとって価値のある、信頼できる情報を提供し続けることにあるでしょう。表面的にはレッドオーシャンに見えても、深く潜ればまだ青い海が広がっているかもしれません。
会話風コメント:成功者たちの「始めたきっかけ」と戦略
Eさん(プログラミングブログ運営): 「元々IT企業で営業だったんですが、エンジニアと話す機会が多くて。自分でも作れたら面白いだろうなって、軽い気持ちでスクールに通い始めたのがきっかけです。ブログは、その学習記録というか、備忘録のつもりで始めました。『初心者が躓きやすいポイント』とか『非エンジニアでも分かる〇〇の解説』みたいな記事を書いてたら、同じような境遇の人からアクセスが増えてきて。戦略としては、難しい専門用語を避け、図解を多く使うことを意識しましたね。あとは、自分が実際に使ってみて良かったツールや参考書を正直にレビューすること。それが信頼に繋がったのかなと思います。今はスクールのアフィリエイトが主な収益源です。」
Fさん(副業紹介ブログ運営): 「シングルマザーで、子供との時間を確保しながら収入を増やしたくて。最初はクラウドソーシングでWebライターを始めたんです。その経験を発信しようと思ったのがブログの始まりですね。『未経験から月5万稼ぐまでのロードマップ』みたいな記事が人気で。読者さんから『他にもおすすめの副業は?』って聞かれることが増えたので、自分が試したポイ活とか、ブログ運営そのものについても書くようになりました。戦略っていうか、とにかく『等身大』でいることですかね。カッコつけずに、失敗談も隠さず書く。あとは、読者さんからの質問には丁寧に答える。その積み重ねでファンが増えていった感じです。収益はアドセンスと、ライティング教材のアフィリが半々くらいかな。」
Gさん(マッチングアプリ比較ブログ運営): 「僕自身、彼女探しに苦労してて(笑)、色んなマッチングアプリを試してたんです。その実体験を元に、『このアプリはこういう人向け』『こういうメッセージはNG』みたいなのを赤裸々に書いたら、結構反響があって。始めたきっかけは、まあ、自分の経験をネタにしよう、くらいの軽いノリでした。戦略としては、各アプリの『ターゲット層』を明確にして、比較記事を徹底的に作り込んだこと。あとは、男性向け・女性向け両方の視点を入れるように心がけました。意外と女性読者も多いんですよ。収益はアプリの登録アフィリエイトがメインですね。単価が高いので、少ないアクセスでも結構な額になります。」
彼らの話から見えてくるのは、必ずしも最初から緻密な戦略があったわけではない、ということです。自身の経験や興味、あるいは課題解決の過程が、自然とブログのテーマとなり、読者の共感を呼んでいった。そして、読者の反応を見ながら、徐々に戦略を練り上げていった、という側面が強いようです。もちろん、闇雲に始めたわけではなく、どこかで「これならいけるかも」という手応えや、市場のニーズを感じ取っていたはずです。あなたの「きっかけ」や「戦略」は、どこに隠れているでしょうか? 次は、絶対に手を出してはいけないジャンルについて、その理由を深く掘り下げていきます。
絶対に避けるべきジャンルとその理由とは?
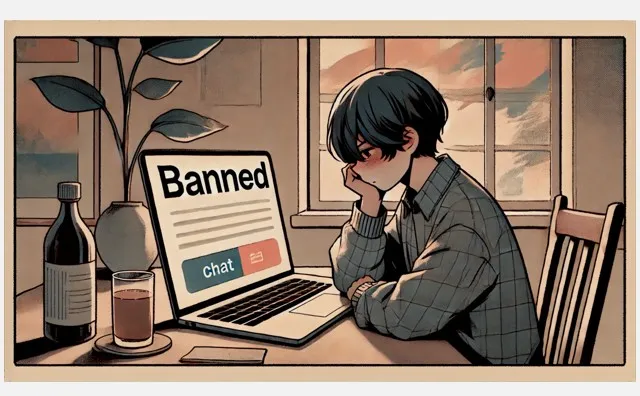
ブログで成功するためには、「何をやるか」と同じくらい、「何をやらないか」が重要です。魅力的に見えるジャンルでも、実は大きなリスクが潜んでいたり、構造的に収益化が困難だったりするケースは少なくありません。知らずに足を踏み入れてしまうと、時間と労力を浪費するだけでなく、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性すらあります。
ここでは、特に初心者が避けるべき代表的なジャンルとその明確な理由について解説していきます。これらの“落とし穴”を知っておくことは、無駄な失敗を回避するための重要な知恵となるでしょう。
YMYL(Your Money or Your Life)領域が鬼門なワケ
ブログジャンル選びにおいて、最も注意すべき、そして可能であれば避けるべきなのが「YMYL」と呼ばれる領域です。YMYLとは「Your Money or Your Life」の頭文字を取った言葉で、文字通り、人々のお金や健康、安全、将来の幸福に大きな影響を与える可能性のある情報分野を指します。
Googleは、検索品質評価ガイドラインの中で、YMYLに関する情報に対しては特に厳しい基準を設けています。なぜなら、これらの分野で誤った情報や質の低い情報が拡散されると、ユーザーの人生に深刻な悪影響を及ぼしかねないからです。例えば、不確かな健康情報によって病状が悪化したり、誤った金融情報によって財産を失ったりするような事態を防ぐ必要があるのです。
具体的にYMYLに該当するジャンルとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 医療・健康: 病気、症状、治療法、医薬品、サプリメント、メンタルヘルス、ダイエット法など
- 金融: 投資(株式、FX、仮想通貨※)、保険、ローン、クレジットカード、税金、年金、不動産取引など
- 法律: 離婚、相続、事故、労働問題など
- ニュース・時事問題: 災害情報、公共政策、国際情勢など(特に信頼性が重要なもの)
- 公的情報: 選挙、行政サービス、社会保障制度など
- 特定のグループ: 人種、宗教、性別、性的指向などに関する情報
- 安全性: 製品リコール、防災情報、護身術など
- 教育: 進学情報、学費、奨学金など
- 幸福・生活: 住宅購入、重要な買い物(自動車など)、キャリア選択(転職含む場合あり)など
これらのYMYLジャンルにおいて、Googleが検索順位を決定する際に最も重視するのが「E-E-A-T」と呼ばれる要素です。
- Experience(経験): そのトピックに関する実体験があるか
- Expertise(専門性): その分野における専門知識やスキルがあるか
- Authoritativeness(権威性): その情報源が、その分野で広く認知され、信頼されているか(例:公的機関、専門学会、著名な専門家)
- Trustworthiness(信頼性): サイト全体や運営者が信頼できるか(透明性、安全性、正確性など)
個人ブログが、これらの要素、特に「権威性」と「信頼性」において、公的機関や大手企業、専門家サイトと同等の評価を得ることは極めて困難です。たとえ医師や弁護士などの有資格者が個人でブログを運営していても、そのブログ自体が社会的に広く認知され、権威ある情報源として認められていなければ、上位表示は難しいのが現状です。ましてや、専門資格を持たない一般のブロガーが、個人の意見や体験談だけでYMYLジャンルの記事を書いても、検索結果の上位に表示される可能性は非常に低いと言わざるを得ません。
「士業などの特別な資格を持たない一般のブロガーが、YMYLのジャンルで勝ち筋を見出すのは事実上不可能」と断言されているのは、こうした背景があるからです。「専門家でないなら、YMYLは避けたほうが無難なジャンル」と結論付けています。
もちろん、絶対に不可能というわけではありません。特定のニッチな領域で、自身の深い経験(Experience)を元にした信頼性の高い情報発信を続ければ、評価される可能性はゼロではありません。しかし、それは非常に茨の道であり、Googleのアルゴリズム変更によって、ある日突然評価が覆されるリスクも常に付きまといます。
「YMYLを避けたからといって、必ずうまくいくわけではないので、『避けられたら避ける』くらいの気持ちでOK」という少し緩やかな見解も示されていますが、これは「どのジャンルでも成功は簡単ではない」という前提に立った上での意見でしょう。
リスクを最小限に抑えたい初心者にとっては、やはり積極的に避けるべき領域であることに変わりはありません。時間と労力をかけたコンテンツが、Googleの評価基準によって日の目を見ない可能性がある。この事実は、ジャンル選定において重く受け止めるべきです。
単価は高いけど危険?承認率が低いジャンルの実態
アフィリエイト案件の中には、1件あたりの報酬単価が非常に高く設定されているものがあります。例えば、数万円といった報酬を見ると、「これを数件成約させれば、すぐに大きな収益になる!」と心が躍るかもしれません。しかし、高単価案件には、しばしば「承認率の低さ」という落とし穴が潜んでいます。
よくある具体例として挙げられているように、
- リフォームの見積もり依頼
- 保険の無料相談申し込み
- クレジットカードの発行申し込み
- エステサロンや美容外科の無料カウンセリング予約
などは、成果発生(申し込みや予約)から最終的な契約や来店、審査通過といった「成果承認」までのハードルが比較的高い傾向にあります。ユーザーが申し込んだ後にキャンセルしたり、審査に落ちたり、あるいは来店しなかったりするケースが少なくないためです。
例えば、報酬単価5万円の案件があったとします。10件の申し込み(成果発生)があり、合計50万円分の報酬が発生したとしても、承認率がわずか10%だったらどうでしょうか? 実際に受け取れる報酬は5万円にしかなりません。単価5,000円で承認率80%の案件を10件発生させた方が、よほど効率的です(報酬4万円)。
承認率は、広告主側の都合やビジネスモデルに依存する部分が大きく、ブロガー側の努力だけでは改善が難しい場合が多いのが厄介な点です。
「承認率はメディア側の努力による改善が難しいため、そのジャンル自体を避けるのが無難」と指摘されています。
もちろん、全ての高単価案件の承認率が低いわけではありません。しかし、特に「無料〇〇」系の申し込みや、その後に審査や来店が必要となるようなサービスを紹介する場合は、承認率について事前に確認しておくことが非常に重要です。ASPの管理画面で確認できる場合もありますが、非公開の場合は、担当者に問い合わせる、あるいは同ジャンルの経験者の情報を集めるなどして、リスクを把握しておく必要があります。
「高単価」という魅力的な響きだけに惑わされず、その裏にある「承認率」という現実を冷静に見極めること。これもまた、賢明なジャンル選びの要諦と言えるでしょう。せっかくの努力が水の泡とならないために、注意が必要です。
収益化手段が限られる「趣味系ジャンル」の盲点
「自分の大好きな趣味についてブログを書きたい!」 これは、ブログを始める動機として非常に自然で、素晴らしいことです。情熱を込めやすく、記事を書くこと自体が楽しい。継続もしやすいでしょう。しかし、「稼ぐ」という視点で見ると、多くの「趣味系ジャンル」には大きな盲点が存在します。それは、「収益化の手段が限られる」という点です。
「書籍レビューブログ」の例は、この問題を象徴しています。書籍を紹介する場合、主な収益化手段はAmazonアソシエイトや楽天アフィリエイトになります。
しかし、これらのプラットフォームでの書籍の紹介料率は数%程度と低く、書籍自体の単価も比較的安いため、1冊売れても数十円程度の報酬にしかならないケースがほとんどです。
月に数万円稼ぐには、膨大なアクセスと販売数を必要とし、現実的には非常に困難です。結果として、「月に1000円前後の利益を稼ぐのがやっとだった」という状況に陥ってしまいました。
これは書籍に限った話ではありません。
- 映画レビュー: DVDや関連グッズの紹介(低単価)、VODサービスへの誘導(単価はやや高いが競合多し)
- 音楽レビュー: CDやダウンロード販売の紹介(低単価)、ライブチケット(期間限定)
- ハンドメイド作品紹介: 材料販売(低単価)、自身の作品販売(制作・販売の手間がかかる)
- 特定のコレクション(切手、コインなど): 関連書籍や道具の紹介(ニッチで低単価)、専門業者への誘導(案件が少ない)
- マイナーなスポーツやゲーム: 関連グッズ(市場が小さい)、イベント告知(期間限定)
もちろん、Google AdSense(クリック報酬型広告)を貼るという手もありますが、アドセンスだけで大きな収益を上げるには、やはり相当なアクセス数が必要です。また、趣味系のジャンルは、情報収集や比較検討というよりは、純粋な楽しみや共感を求めてアクセスするユーザーも多く、広告クリック率や商品購入率が他のジャンルに比べて低くなる可能性も考えられます。
「広告主や案件が少ないジャンルは選ばない」というアドバイスも、この点に関連します。紹介できる広告が少なければ、収益化の道は狭まります。また、もし数少ない広告主が撤退してしまった場合、収益源を失うリスクもあります。
だからといって、趣味ブログがダメだというわけではありません。収益を度外視して、純粋に情報発信や交流を楽しむのであれば、素晴らしい活動です。しかし、「ブログで稼ぎたい」という目標があるならば、その趣味ジャンルに「適切な収益化手段(ある程度の単価と需要が見込めるアフィリエイト案件など)が存在するかどうか」を、始める前に冷静に検討する必要があります。
もし、どうしても好きな趣味でブログを書きたい、かつ収益も得たいのであれば、
- その趣味に関連する、より高単価なジャンルと組み合わせる(例:旅行ブログ × クレジットカード・旅行保険)
- 自身の専門性を活かして、情報商材やコンサルティングを提供する
- 圧倒的なアクセス数を集めてアドセンス収益を最大化する
といった、高度な戦略が必要になるでしょう。初心者にとっては、ややハードルが高いかもしれません。
失敗談コメント:コンテンツは良くても収益ゼロだった話
Hさん(映画レビューブログ運営): 「映画が大好きで、年間100本以上観るんです。その熱量でブログを始めたら、結構アクセスは集まったんですよ。SNSでもシェアされたりして。読者さんから『レビュー参考になります!』って言われると嬉しくて、どんどん記事を書いてました。でも、収益はほぼゼロ(苦笑)。AmazonでDVD紹介しても、月に数百円とか。VODのアフィリもやってみたけど、大手サイトには勝てなくて全然成約しない。コンテンツには自信あったんですけどね…。結局、サーバー代も稼げないから、更新止めちゃいました。好きと稼ぐは別なんだなって痛感しましたね。」
Iさん(マイナースポーツ応援ブログ運営): 「私がやっている〇〇っていうスポーツ、競技人口が少なくて。少しでも普及させたくてブログを始めたんです。ルール解説とか、選手の紹介とか、試合レポートとか。コアなファンはついてくれて、コメント欄も盛り上がったんですけど、マネタイズが本当に難しかった。関連グッズもほとんどないし、アフィリエイト案件なんて皆無。アドセンス貼っても、アクセス数が少ないから雀の涙。完全にボランティア状態でしたね。ブログ自体は楽しかったけど、『これで生活できたらな…』なんて夢は、早々に諦めました。」
Jさん(ハンドメイド作品紹介ブログ運営): 「自分で作ったアクセサリーを紹介するブログをやってました。作り方とか、材料の仕入れ先とかも公開して。読者さんから『作ってみました!』って報告もらうと嬉しかったな。でも、収益は材料のアフィリくらい。1個売れても数円とかの世界。自分の作品を売ることも考えたけど、制作から梱包、発送まで全部一人でやるのは大変で…。ブログで人気が出ても、それが直接的な収益に結びつかないのがもどかしかったですね。結局、今は趣味の範囲で細々と続けてる感じです。」
これらの声は、コンテンツの質や読者からの評価が高くても、収益化の仕組みが伴わなければ「稼ぐ」ことには繋がらない、という現実を物語っています。「良いものを作れば、お金は後からついてくる」というのは、残念ながらブログの世界では必ずしも真実ではありません。ジャンル選定の段階で、「どうやって収益を上げるのか?」という具体的な道筋を描けているか。それが、失敗を避けるための重要な問いかけとなるのです。では、どうしてもジャンルを決めきれない時、最後の手段としてどんな方法があるのでしょうか? 次の章で探っていきましょう。
どうしても決められない時のジャンル決定法

ここまで、ジャンル選びの重要性、基準、おすすめ、そして避けるべき点について解説してきました。しかし、それでもなお、「どのジャンルを選べばいいのか、決められない…」と頭を抱えている方もいるかもしれません。情報が多すぎて混乱したり、どのジャンルも一長一短に見えて、決断を下せない。そんな状況は、決して珍しいことではありません。しかし、悩み続けて立ち止まっているだけでは、何も始まりません。
ここでは、どうしてもジャンルを決められない時のための、具体的な「決定法」や「考え方」を、データに基づきご紹介します。最後のひと押し、あるいは発想の転換が、あなたを次の一歩へと導くかもしれません。
ASPから逆算する!広告案件を“起点”に考える発想
通常、ブログのジャンル選びは、「自分の興味関心」や「市場のニーズ」からスタートすることが多いでしょう。しかし、どうしても決められない場合、発想を逆転させて、「紹介できる広告案件(アフィリエイト案件)」を起点に考えてみる、というアプローチが有効です。
ここで提案されているステップは、まさにこの考え方に基づいています。
ステップ1:ASPの管理画面をとにかく眺める
まずは、A8.netやもしもアフィリエイトといった主要なASPに登録し、管理画面にログインしてみましょう。目的は、「世の中にはどんな広告があるのかを知る」ことです。特に「新着プログラム(案件)」や、カテゴリー別の案件一覧などを、先入観を持たずにざっと眺めてみます。
「こんなサービスにもアフィリエイトがあるんだ!」という発見があるかもしれません。Wi-Fi、転職、不動産、アクセサリー、ゲーム、さらには「臍帯血保管」といった意外な案件まで、多種多様な広告が存在します。
ステップ2:気になる案件をピックアップし、詳細をチェック
眺めている中で、「これ、ちょっと面白そう」「使ったことあるな」「詳しく知りたいかも」と感じる案件がいくつか出てくるはずです。それらをリストアップし、詳細情報を確認します。
- 報酬: 定額か定率か、金額はいくらか。「まず1000円以上」を目安としていますが、こだわりすぎず、500円程度でも興味が持てれば候補に残します。ただし、Amazonなどの極端に低いものは注意。
- 知名度(認知度): その商品やサービスが、世間一般にどの程度知られているか。CMなどで見かけるか? 初心者は知名度の高い商品の方が圧倒的に扱いやすいです。「ライバルが多そう」と敬遠せず、むしろ「売りやすい」と捉えるべきです。
- 承認条件: どんな条件を満たせば成果として承認されるのか。無料登録だけか、購入や来店が必要かなども確認します。
ステップ3:関連キーワードでGoogle検索(ライバルをチラ見)
ピックアップした案件に関連するキーワード(例:「〇〇(商品名) 口コミ」「△△(サービス名) おすすめ」)でGoogle検索してみます。どんなサイトが上位に表示されているか、どんな記事を書いているかを軽くチェックします。
ここで「勝てるか?」と深く分析しすぎて萎縮する必要はありません。「ふーん、こんな感じで紹介してるんだな」と参考にする程度でOKです。
ステップ4:その案件を紹介するブログを構想する
ステップ2と3を踏まえ、「もし自分がこの広告を紹介するブログを作るなら、どんなテーマで、どんな切り口で書けるだろうか?」と考えてみます。
- どんな読者(ターゲット)に向けて?
- どんな悩みを解決できる?
- 他のサイトにはない、自分ならではの価値は提供できる?(体験談など)
この「ASPから逆算する」アプローチのメリットは、最初から「収益化の手段(紹介する広告)」が明確になっていることです。「記事は書いたけど、貼る広告がない…」という事態を避けられます。また、具体的な広告案件を見ることで、漠然としていたブログのテーマが具体化しやすくなる効果も期待できます。
興味関心だけで選ぶと収益化で悩み、収益性だけで選ぶと継続で悩む。その間を取る、あるいは新たな視点を与えてくれるのが、この「広告案件起点」の発想と言えるでしょう。決められない時の突破口として、試してみる価値は十分にあります。
「30記事書けるか?」でネタの持続性を見極めよう
ジャンルの候補がいくつか挙がった、あるいは広告案件起点でテーマが見えてきた。しかし、まだ不安が残るかもしれません。「このテーマで、本当にブログを続けていけるのだろうか?」その不安を解消するための一つの具体的な方法が、「そのテーマで、最低30記事分のタイトル(あるいは簡単な内容)をリストアップできるか試してみる」ことです。これは、ネタの「持続性」を見極めるための有効なテストです。
なぜ30記事なのでしょうか? ブログがある程度の形になり、検索エンジンからも評価され始めるには、最低でも数十記事は必要と言われています。30記事というのは、その初期段階を乗り越え、さらにブログを育てていくための「最低限のネタのストックがあるか」を確認する目安となります。
やり方は簡単です。選んだジャンルやテーマについて、思いつく限りの記事タイトルや、書きたい内容のキーワードを、箇条書きでどんどん書き出していきます。
- 基本的な解説記事(〇〇とは?、仕組み、メリット・デメリット)
- 比較記事(AとBの違い、おすすめランキング)
- レビュー記事(実際に使ってみた感想、評価)
- ノウハウ記事(使い方、始め方、攻略法、コツ)
- Q&A記事(よくある質問と回答)
- 体験談(成功談、失敗談)
- 周辺情報(関連ニュース、業界動向)
- ターゲット別の記事(初心者向け、〇〇な悩みを持つ人向け)
もし、このリストアップがスムーズに進み、30個、あるいはそれ以上(50個、100個…)のアイデアが次々と湧き出てくるようであれば、そのジャンルはあなたにとってネタの宝庫であり、長期的にコンテンツを生み出し続けられる可能性が高いと言えます。記事を書く上での引き出しが多い、ということです。
逆に、必死にひねり出しても5個や10個程度しか思いつかない、あるいはすぐに手が止まってしまうようであれば、そのジャンルはあなたにとって、現時点では深掘りするのが難しい、あるいは興味関心の範囲が狭いのかもしれません。無理にそのジャンルで始めても、早い段階でネタ切れに陥り、更新が滞ってしまうリスクが高いでしょう。
「5個くらいしか思いつかない場合は、そのジャンルは途中でネタ切れになるかも…」と警告しています。さらに、リストアップした記事数と、自分が1週間に書ける記事数(最初は1~2記事程度と仮定)から、ブログがある程度の形になるまでの期間を想像してみることも勧めています。もし200記事必要なブログ構想で、週に1記事しか書けないなら、完成まで約4年かかる計算になります。そのペースで継続できるか、現実的に考える必要があります。
ここで非常に重要な注意点として、「AIに頼りすぎないこと」を挙げています。「〇〇に関するブログ記事のネタを50個教えて」とChatGPTのようなAIに丸投げするのは簡単ですが、それは「あなた自身のブログ」ではなくなってしまいます。AIが生成した、どこかで見たようなアイデアリストを元に記事を書いても、熱意は込められず、いずれ書くのが辛くなるでしょう。そして、AIが書いたような無味乾燥な記事では、読者の心は動かせず、収益にも繋がりません。あくまで、自分の頭で考え、自分の言葉で語れるネタがどれだけあるか、を見極めることが重要なのです。
この「30記事テスト」は、単なるネタ出し作業ではありません。そのジャンルに対するあなたの知識、興味、そして情熱の深さを測るバロメーターなのです。
雑記ブログからの“ジャンル特化”はアリかナシか?
どうしても特定のジャンルに絞り込めない場合の選択肢として、「雑記ブログ」から始める、という方法があります。雑記ブログとは、特定のテーマに縛られず、書き手が興味を持った様々な事柄について自由に書いていくスタイルのブログです。
雑記ブログのメリット:
- 始めやすい: ジャンル選びに悩む時間を短縮でき、すぐに書き始められます。
- ネタ切れしにくい: 自分の日常や関心事が全てネタになるため、比較的継続しやすいです。
- 自分の得意・興味を発見できる: 色々なテーマで書く中で、読者の反応が良い記事や、自分が書いていて楽しいテーマが見つかることがあります。
どうしても決められない場合の選択肢として雑記ブログが挙げられています。「初めは3~5つ程度の興味関心があるジャンルについて記事を書き、読者の反応が良かったジャンルに絞り込んでいく方法もいい」、「とりあえず雑記ブログから始めて見るのもあり」といった具合です。
雑記ブログのデメリット:
- 専門性が低く評価されにくい: Googleは専門性の高いサイトを評価する傾向があるため、雑多なテーマを扱う雑記ブログは、検索エンジンからの集客(SEO)で不利になりやすいです。
- ターゲットがぼやける: 様々なテーマを扱うため、どんな読者に向けたブログなのかが分かりにくく、ファンが付きにくい可能性があります。
- アフィリエイト収益化が難しい: 読者の興味関心が分散しているため、特定の商材を紹介しても成約に繋がりにくい傾向があります。
よくあるQ&Aでは、「アクセスの集めやすさやアフィリエイトの収益性を追求するなら特化ブログ」「雑記ブログは検索エンジンからの集客が難しくアフィリエイトにも向いていない」と、収益化の観点からは特化ブログに軍配を上げています。
では、「雑記ブログから始めて、後からジャンルを特化する」という戦略はアリなのでしょうか?
結論から言うと、**「アリだが、注意が必要」**です。
雑記ブログとして運営していく中で、特定のカテゴリーの記事だけが突出してアクセスを集めたり、読者からの反響が大きかったりした場合、そのジャンルにブログの方向性をシフトしていく(特化していく)のは有効な戦略です。実際に、この方法で成功しているブロガーもいます。最初にリスクを取らずに始め、市場の反応を見ながら自分の勝ち筋を見つけていく、という合理的なアプローチとも言えます。
しかし、注意点もあります。よくあるQ&Aにあるように、「検索エンジンの評価が分散する」可能性があるため、全く関係のないジャンルへ急に方向転換するのは得策ではありません。もし、雑記ブログとして書いてきたテーマと全く異なるジャンルに特化したい場合は、新しいブログを別途立ち上げた方が良い場合もあります。また、既存の読者が離れてしまう可能性も考慮する必要があります。
理想的なのは、雑記ブログとして書き始めた複数のテーマの中から、隣接する分野や関連性の高い分野に徐々に絞り込んでいく形です。例えば、「旅行」「グルメ」「カメラ」について書いていたブログが、読者の反応を見て「子連れ旅行特化ブログ」や「グルメ旅専門ブログ」に進化していくようなイメージです。
雑記ブログは、ジャンル選びの「猶予期間」あるいは「実験場」と捉えることができます。しかし、収益化を目指すのであれば、いずれどこかのタイミングで「特化」を意識する必要がある、ということは念頭に置いておくべきでしょう。
最終決断:「やってみなはれ!」の精神
ここまで様々な決定法を見てきましたが、最も強調しているのは、結局のところ**「とにかく始めてみること」**の重要性です。
- 初心者が最初から完璧なジャンルを選ぶのはほぼ不可能。
- やってみないと、自分に書けるか、どんな記事が書けるか分からない。
- 悩んでいる時間は1円にもならないが、始めれば経験値が貯まる。
- 「このジャンルはダメだった」と分かるだけでも大きな前進。
サントリー創業者の鳥井信治郎氏の有名な言葉「やってみなはれ」を引用し、「1週間以上悩むのは時間の無駄」「悩んでいるフリをして行動しない理由を探しているだけかも」とまで言い切っています。そして、究極の手段として、「期限ギリギリになったら、ASPの新着案件の一番上を選んで、何も考えずにGO!」とすら推奨しています。
これは、完璧な準備に固執して行動できないよりも、多少見切り発車でも、まず一歩を踏み出すことの方がはるかに重要だ、というメッセージです。失敗する可能性は高い。しかし、その失敗から学び、次に活かせばいい。行動しなければ、成功も失敗もありません。
もしあなたが、今まさにジャンル選びで悩み、手が止まっているのなら。この「やってみなはれ!」の精神を、少しだけ心に留めてみてください。完璧な地図などなくても、漕ぎ出してみる勇気が、新しい景色を見せてくれるかもしれません。
コメント:最終的に成功した人は、こうやって決めた!
Kさん(転職ブログ運営): 「僕の場合、最初は副業ブログみたいな感じで、Webライターとかブログ運営について書いてたんです。でも、自分の本業が人事だった経験を活かして、転職相談に乗る記事を書いたら、ものすごく反響があって。それで、『これだ!』と。ASP見たら転職系は単価も高いし、自分の経験も専門性も活かせる。まさに、市場ニーズと自分の強みがカチッとハマった瞬間でしたね。そこから一気に転職ジャンルに特化しました。決断のポイントは、やっぱり『読者の反応』と『自分の経験が活かせるか』、そして『収益性』の3つが揃ったことかな。」
Lさん(ガジェットレビューブログ運営): 「正直、最初は完全に雑記ブログでした。好きなガジェットのこと、読んだ本のこと、旅行のこと…本当に脈絡なく。でも、アクセス解析見てたら、なぜか特定のメーカーのイヤホンレビュー記事だけ、ずーっと読まれてることに気づいたんです。『もしかして、この分野なら勝てる?』と思って、試しに他のイヤホンレビュー記事を増やしてみたら、やっぱりアクセスが伸びて。そこからですね、ガジェット、特にオーディオ系に特化しようと決めたのは。ASP案件も探したら結構あったし。決め手は『データ(アクセス解析)』と『書いてて楽しい』ことでしたね。やっぱり自分が好きなものじゃないと、細かいレビューなんて書けないですよ。」
Mさん(オンライン英会話比較ブログ運営): 「決められなくて、1ヶ月くらい悩んでました(笑)。でもある時、成功してるブロガーさんの『悩むくらいなら、一番報酬が高い案件を選んで、それを売る方法を死ぬ気で考えろ』っていう記事を読んで、目が覚めて。それで、ASPで一番単価が高かったオンライン英会話の案件を選んで、『よし、これでいく!』って無理やり決めたんです。もちろん、英語は好きでしたけど、特別詳しかったわけじゃない。だから、最初の3ヶ月は、自分がユーザーになってサービスを使い倒して、競合サイトを徹底的に分析して、記事を書きまくりました。最初は全然ダメでしたけど、半年くらい経った頃から、ポツポツ成果が出始めて。決めた理由は…もう、半ばヤケクソでしたけど(笑)、でも『これをやる!』って決めたからこそ、必死になれたんだと思います。」
三者三様ですが、彼らに共通しているのは、何らかの「きっかけ」や「根拠」を見つけ、最終的には「決断」し、「行動」に移したということです。読者の反応、アクセスデータ、自分の経験、収益性、あるいは成功者の言葉…。何がトリガーになるかは分かりません。しかし、悩み続けるフェーズから抜け出し、「これでいく」と腹を括る瞬間が、成功への扉を開く鍵となるのかもしれません。あなたにとっての「決断の根拠」は、もうすぐそこにあるのかもしれません。
まとめ|あなたのブログジャンルは“稼げる土俵”か?
さて、ブログジャンル選びの長い旅も、いよいよ終着点です。なぜ多くの人が失敗するのか、その理由から始まり、稼げるジャンルを見極める5つの基準、具体的なおすすめジャンル、避けるべき落とし穴、そして決められない時の最終手段まで、様々な角度から掘り下げてきました。
最終的に問いたいのは、これです。あなたが今、選ぼうとしているジャンル、あるいは既に歩み始めているその道は、本当に「稼げる土俵」なのでしょうか? それとも、努力が報われにくい、厳しい茨の道なのでしょうか?
成功する人は「完璧なジャンル」を選ばない
ここまで読んで、「やっぱり完璧なジャンルなんて見つからない…」と感じた方もいるかもしれません。収益性は高いけど競合が強い、市場は大きいけど自分の興味と合わない、興味はあるけど収益化が難しい…。全ての基準を完璧に満たす理想のジャンルなど、そう簡単には見つからないものです。
しかし、ここで重要な視点があります。それは、ブログで成功している人たちが、必ずしも最初から「完璧なジャンル」を選んでいたわけではない、ということです。
初心者が最初から大当たりを引き当てる確率は高くありません。むしろ、「失敗する可能性の方が高い」と考えるくらいが現実的かもしれません。多くの成功者は、
- 最初は手探りで始め、試行錯誤の中で「当たり」を見つけていった(雑記からの特化など)
- 途中で方向転換やジャンルのピボット(軸足移動)を行った
- 市場の変化に合わせて、ブログの内容を進化させてきた
のです。
彼らが持っていたのは、「完璧な選択をする能力」ではなく、「行動し、学び、修正する能力」だったのではないでしょうか。
「やってみなはれ」の精神でまず一歩を踏み出し、アクセス解析や読者の反応という「現実」からフィードバックを得て、より良い方向へと舵を切っていく。そのプロセスの中で、自分にとっての「稼げる土俵」を、いわば”作り上げていった”とも言えます。
完璧なジャンル選びに固執し、悩み続けて行動できないでいるよりも、たとえ70点の選択であっても、まず始めてみること。そして、走りながら考え、改善し続けていくこと。それこそが、変化の激しいブログの世界で生き残り、成功を掴むための、最も確実な道なのかもしれません。
失敗を恐れる必要はありません。「このジャンルは違った」と気づくこと自体が、次への大きな一歩となるのですから。
考察:ジャンル選びの鍵は、“自分の中”にあるかもしれない
市場規模、競合、収益性、トレンド…。ジャンル選びにおいて、これらの外部要因を分析することは確かに重要です。しかし、それだけでは見えてこない、もう一つの大切な要素があります。それは、他ならぬ「あなた自身」です。
最終的に、ブログを書き、育て、読者と向き合っていくのは、AIでも他の誰かでもなく、あなた自身です。あなたの情熱、興味、経験、知識、価値観、そして「何を伝えたいのか」という思い。それらが伴わなければ、どんなに市場的に有望なジャンルであっても、魂のこもらない、薄っぺらなブログになってしまうでしょう。
- あなたが、寝る間も惜しんで語りたくなることは何ですか?
- あなたが、他の人よりも少しだけ詳しいことは何ですか?
- あなたが、過去に悩み、乗り越えてきた経験は何ですか?
- あなたが、解決したい、あるいは貢献したいと思える社会の課題は何ですか?
これらの問いに対する答えの中にこそ、あなただけの「稼げる土俵」を見つけるヒントが隠されているのかもしれません。
もちろん、市場のニーズを無視して独りよがりになっては意味がありません。目指すべきは、「市場のニーズ(人々が求めていること)」と「あなた自身の強み・情熱(あなたが提供できる価値)」が重なり合う、スイートスポットを見つけることです。
外部環境の分析(市場、競合、収益性)と、内部環境の分析(自分の適性、経験、情熱)。この両輪がバランス良く噛み合った時、ブログは力強く走り出すのではないでしょうか。
ジャンル選びは、ブログ運営の最初のステップでありながら、最も奥深く、そして本質的な問いを私たちに投げかけます。「自分は何者で、何を成したいのか?」――その問いと向き合うプロセスそのものが、あなたのブログを、そしてあなた自身を、成長させてくれるのかもしれません。
さあ、羅針盤は手にしました。あとは、勇気を持って、あなたの航海へと漕ぎ出すだけです。あなたのブログ旅が、実り豊かなものになることを、心から願っています。
失敗しないブログジャンル選び:初心者が稼げる基準と回避すべき落とし穴
- 多くの初心者は選択肢の多さや情報の洪水でジャンル選びに迷う
- 「稼ぎたい」と「書きたい」のギャップが初心者の決断を鈍らせる
- 収益性の低い趣味系ジャンルやニッチすぎる市場は失敗しやすい
- 競合が強すぎるレッドオーシャン市場への安易な参入は避けるべきだ
- YMYL領域は専門性・権威性が低いとGoogle評価を得にくい
- ジャンル選定は収益性(単価・承認率・売れやすさ)を冷静に評価する
- 将来にわたって需要が見込める市場規模の大きなジャンルを選ぶ
- 競合サイトを分析し、自身の強みを活かせる「切り口」を見つける
- 一時的なブームでなく、長期的に安定アクセスが見込めるか判断する
- 自身の興味・関心や経験・知識と合致するジャンルは継続しやすい
- 報酬単価が高くても承認率が極端に低い案件には注意が必要である
- ASP掲載の広告案件を起点に収益化可能なジャンルを探す方法もある
- 候補ジャンルで30記事以上のネタを具体的に出せるか確認する
- どうしても決められない場合は雑記ブログから始め反応を見る手もある
- 完璧な選択に固執せず、まず行動し試行錯誤する姿勢が成功への近道だ
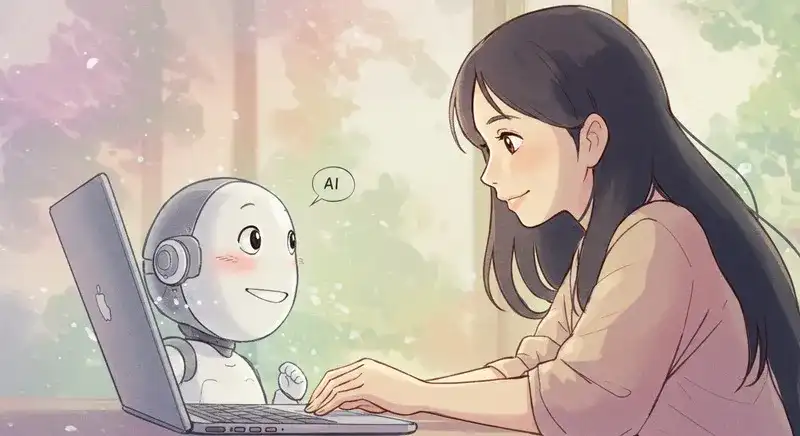
コメント